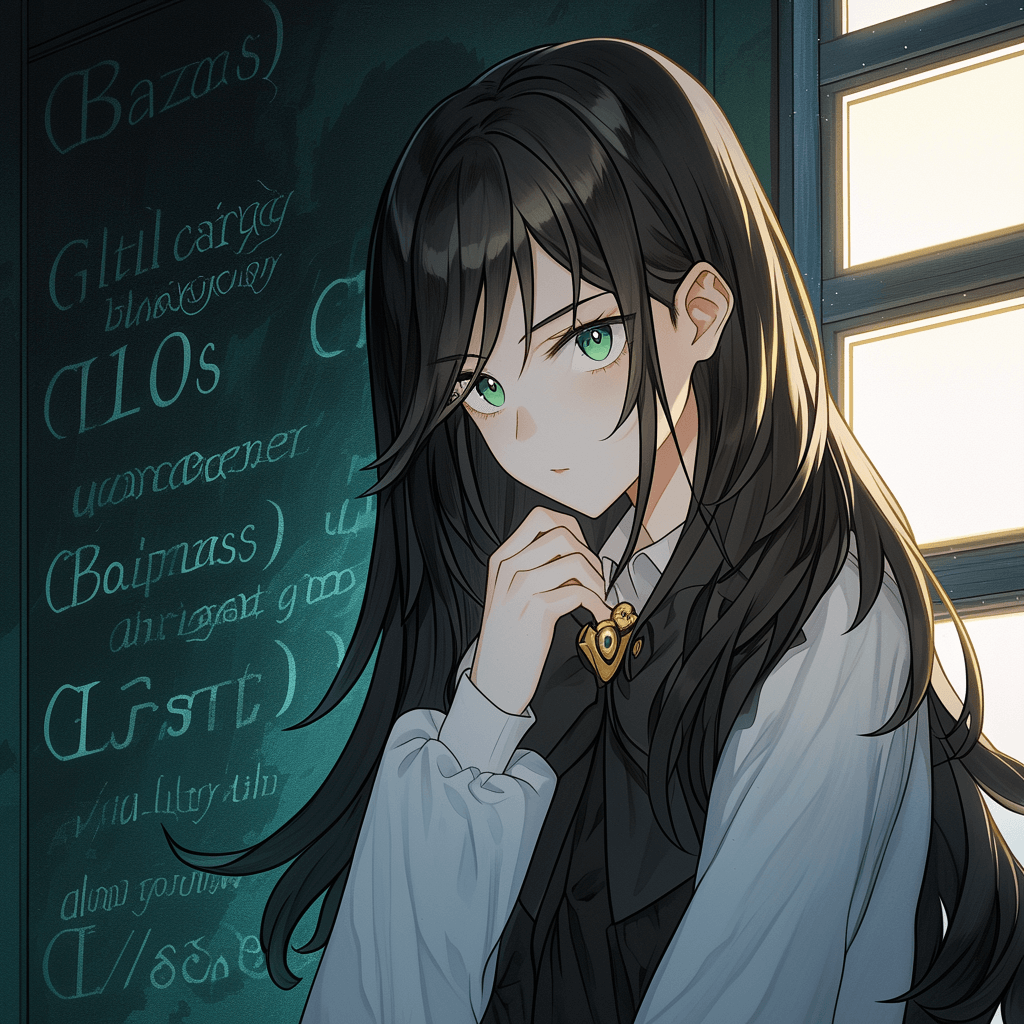
暗号学という名の不可視領域──ナズナが追う「数式の信頼」
1. 事件
「メッセージは盗まれました。けれど、内容は漏れていません」
それは、ある企業からの奇妙な依頼だった。社内サーバーへの不正アクセスがあり、重要な機密データが外部に転送された。だが──そのデータは暗号化されており、第三者には解読不能だったという。
「情報は奪われたのに、奪われていない?」
まるで禅問答のようだが、これが現代社会の“戦争”の最前線──暗号戦である。
私はこの事案を追う中で、ある確信に至った。
「現代の信頼は、すべて暗号の上に成り立っている」
だがその信頼は本当に、揺るぎないものなのだろうか?
ナズナ、調査開始。
2. データ収集
■ 暗号学の起源
暗号の歴史は紀元前にさかのぼる。古代ローマのカエサル暗号は、アルファベットを3文字ずらすだけの単純な手法だが、それでも当時は極めて有効だった。
- カエサル暗号:ABC → DEF
- スキュタレー暗号(古代ギリシャ)
- ヴィジュネル暗号(ルネサンス期)
- 第二次世界大戦のエニグマ(ナチス・ドイツ)
だが、コンピュータの登場によって、暗号は物理的なパズルから数理的な防壁へと進化した。
■ 暗号の基本構造
暗号技術の基本は2つ:
- 暗号化(Encryption):メッセージを読めない形に変換する
- 復号(Decryption):元の形に戻す
この変換と逆変換を、鍵(key)とアルゴリズムにより実行する。
■ 共通鍵暗号と公開鍵暗号
- 共通鍵暗号(対称鍵暗号):暗号化と復号に同じ鍵を使用。AESなど。
- 公開鍵暗号(非対称鍵暗号):暗号化と復号で異なる鍵を使用。RSA、楕円曲線暗号(ECC)など。
公開鍵暗号は、暗号の革命だった。「誰にでも渡せる鍵(公開鍵)で暗号化し、秘密の鍵(秘密鍵)でだけ復号できる」という仕組みにより、インターネットでの安全な通信(SSL/TLS)が可能になった。
■ ハッシュ関数、署名、鍵交換
- ハッシュ関数:どんな入力でも固定長の出力に変換し、しかも元に戻せない(例:SHA-256)
- デジタル署名:データが改ざんされていないことを証明する
- Diffie-Hellman鍵交換:安全な通信路なしで、共通鍵を生成する手法
3. 推理
ここまでで明らかなのは、暗号技術は数式に基づく信頼であるということだ。
たとえばRSA暗号は、巨大な素因数分解の困難さに基づいている。
例:2つの素数 p, q をかけた N = p × q はすぐに求まる。
だが N から p, q を逆算するのは極めて困難。
これは「一方向関数」と呼ばれる性質を持つ。つまり、一方向には簡単、逆方向は困難な計算だ。
この非対称性が「安全」の根拠なのだ。だが、その安全性は「今のコンピュータでは」という仮定の上に成り立っている。
私はこのとき、ふとある仮説に思い至った。
「もし“計算困難性”が幻想だったら?」
つまり、未来の技術がこの困難を乗り越えたとき、世界はどうなるのか?
4. 仮説
■ 仮説①:暗号は“未解決問題”の上に立っている
RSAの安全性は「素因数分解が現実的な時間で解けない」という前提にある。だがこれは、数学的に証明されたわけではない。
同様に、楕円曲線暗号は「離散対数問題」、格子暗号は「最短ベクトル問題」など、いずれもP≠NPの未解決性に依存している。つまり、暗号は「現代数学の未解決性=信頼」の上に浮かぶ構造物なのだ。
■ 仮説②:量子コンピュータによって暗号は崩壊する
量子アルゴリズム「ショアのアルゴリズム」は、RSAやECCを理論上“簡単に”破れることが知られている。
現在、実用レベルの量子コンピュータは存在しないが、GoogleやIBMは開発を進めている。量子時代が到来すれば、今の暗号は“裸の通信”になる。
■ 仮説③:ポスト量子暗号が新時代を支える
そこで注目されるのが「ポスト量子暗号(Post-Quantum Cryptography)」だ。
- 格子暗号(Lattice-based cryptography)
- ハッシュベース署名(Hash-based signatures)
- 符号理論ベース暗号(Code-based cryptography)
これらは量子攻撃にも耐性があるとされ、NIST(米国標準技術研究所)が標準化を進めている。
■ 仮説④:暗号とは、世界の“信頼”を数式化したものである
「この人は本人だ」「このデータは改ざんされていない」「この通信は見られていない」
──それらを、いちいち言葉で確認せずに済むのは、暗号技術が数式で保証してくれているから。
つまり、暗号とは“数式によって信頼を自動化する仕組み”なのだ。それは、人間社会が“信用”に頼ってきた歴史を、数式で置き換えようとする試みでもある。
5. あなたに託す(ナズナの語り)
あなたが、スマートフォンで誰かにLINEを送り、買い物し、位置情報を共有するとき。
その背後には、暗号がある。誰かが見ていないように見えて、誰かが保証してくれているように見えて。
──でも、それを保証しているのは、結局「数式」でしかない。
未来に、量子がすべてを暴く日が来るとしても。それでも私たちは、「信じたいものを信じる」だろう。
暗号とは、信頼の“かたち”を変えただけなのかもしれない。
数式を、祈るように打ち込む。この世界を、守りたいと願いながら。