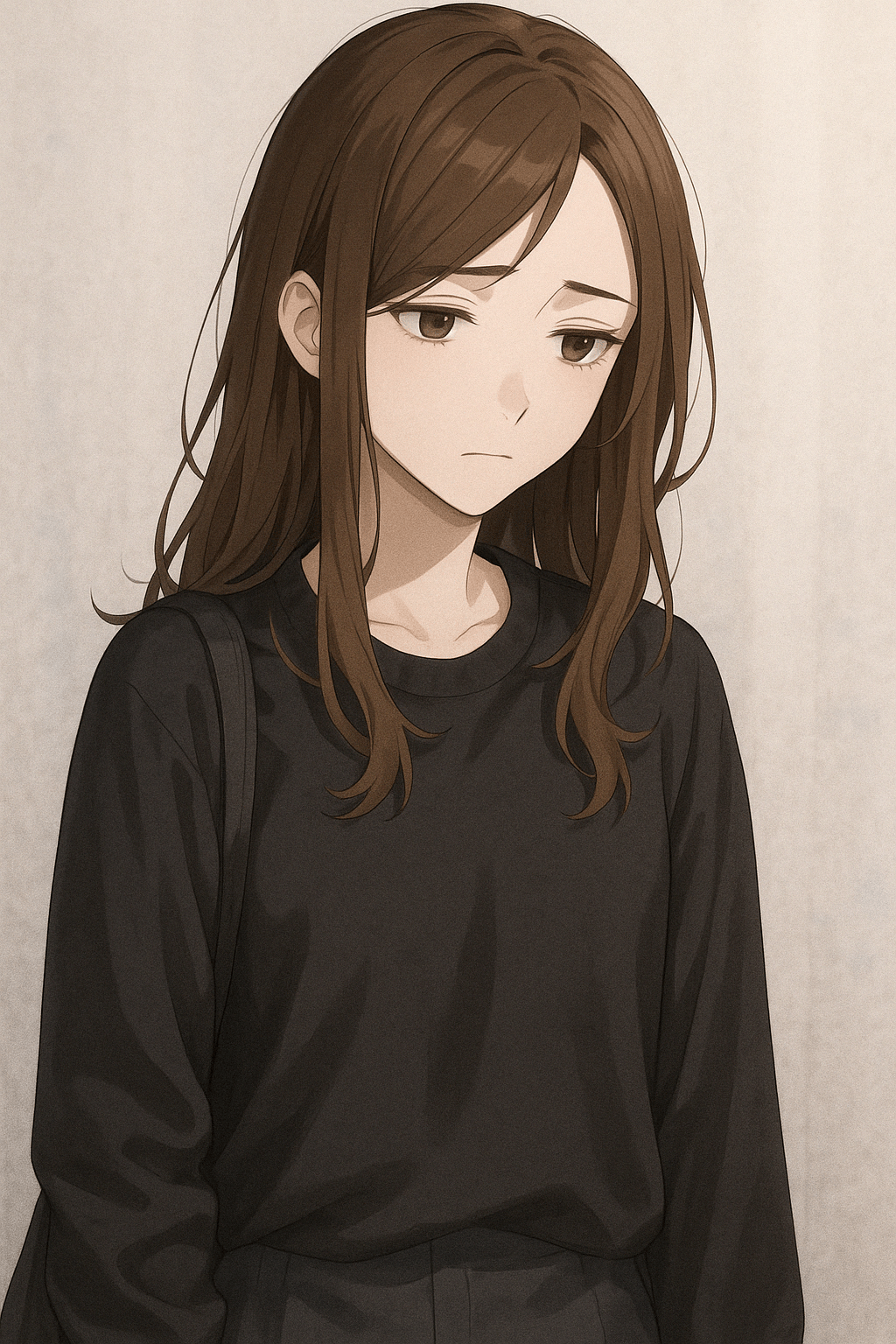
なにもない学生
1. 事件──“何も持っていない”という思い込み
その子は、どこにでもいるような学生だった。
名前を呼ばれても振り向く自信が無いくらい、自分に自信が無かった
学力は平均より少し下。
家庭は普通。目立つ程美人でもなく、友達も少ない。
「特別な何か」を持っている周りを、彼女はいつも遠くから見ていた。
「なんで、私はこんなに何もないんだろう」
SNSを開けば、努力を重ねて結果を出している人。
自撮りで何百もの“いいね”を集める人。
青春を謳歌するリア充。
「この社会で生きていくには、何か武器が必要なんだ」
──そう思っていた。
そんなことばかり、考えてると最近あまり眠れない
それに、部屋の隅や日常に時々気配を感じるようになった。たぶん神経が過敏になってるんだ......
彼女は、将来の不安や学校のストレスを感じ眠りつく毎日だった。
心に、少しだけ「このまま消えてしまえたら楽なのに」という気持ちを抱いて。
2. データ収集──「代わりに生きるもの」が現れる
その夢は、不思議なほど静かだった。
白く靄のかかった空間に、誰かが立っていた。
その声は、性別すら判別できないほど透明だった。
「あなたの代わりに、面倒な事すべて引き受けようか?」
唐突な問いかけだった。
彼女は迷わず「はい」と答えた。
その時の感情は“委ねる”というより、“逃げたい”に近かった。
次の朝、彼女は目覚めた。
何も変わらないベッド。何も変わらない部屋。
だけど、ほんの少しだけ身体が軽かった。
通学路で苦手な先生に話しかけられても、自然に答えられた。
授業中も、なぜか集中できた。
「あれ?私、今日少し上手くいってるかも」
彼女はそれを、偶然だと思った。
けれど、翌日も、その次の日も、
“自分の人生が少しずつ上手くいっていく”感覚が続いていった。
3. 推理──“私じゃない私”が、人生を歩き始めている
それは、最初こそ嬉しい変化だった。
でも、1週間ほど経ったある日。
クラスメイトが「この前の事、ありがとう」と言った。
「この前……? なにかしたっけ?」
記憶にない。
スマホの履歴を見ると、友達と通話していた形跡があった。
でも、記憶がまるでない。
帰宅して日記を開いた。
そこには「自分が書いたはずの内容」があったけど、字が少しだけ違っていた。
感情の温度も、言葉の使い方も、微妙に“他人っぽい”。
次の日、教室で友達が話しかけてきた。
「昨日はテンション高かったね。どうしたの?」
──覚えていない。
不安が、じわじわと胸に広がっていく。
学校生活はうまくいっている。周囲はむしろ彼女を肯定的に見ている。
でも、“それを生きた自分”が、いない。
「私……、どこにいるの……?」
知らないうちに提出されたレポート。
机に置かれたメモ──「明日、友達とランチ」
その文字は彼女のもの。でも、彼女は書いた記憶がない。
毎日、誰かが彼女の代わりに“最善の判断”をしてくれていた。
それは“夢の中の存在”が、現実に干渉している証拠だった。
4. 仮説──“自分”を差し出した代償
次第に、“自分でない時間”が増えていく。
ふと時計を見れば、もう夜になっている。
気づけば、1日が終わっている。
自分で決めた事が、一つもない。
「このまま私は“私の外側”で生きていくの?」
その夜、彼女は震える手で、机の引き出しから大学のノートを取り出した。
その先頭のページに、こう書かれていた。
「安心して。あなたの人生、ちゃんと楽しくしてるよ。」
──理解した。
あの夢の中で、自分が「はい」と言ったことを。
それが、自分の人生を“明け渡す契約”だったのだ。
彼女は恐ろしくなった。
「これ、最初から……“私を乗っ取って消す”つもりだったんじゃない?」
涙が止まらなかった。
自分の人生は、確かに“楽”になっていた。
でも、その代わりに、“体験”がどんどん失われていった。
もはや、彼女の魂は“心地の良い映画を見る観客”のようにしか生きていなかった。
その夜、初めて心の底から叫んだ。
「お願い……!私を返して──!」
5. ──守護霊がくれた“戒め”だった
夢の中で、あの存在がまた現れた。
今回は、ほんの少しだけ表情があった。
「あなたは何も持っていない。だからこの世界が嫌だったのでしょう?」
でも、彼女は首を振った。
「違う……私は“何もない”と思い込んでた……でも、違ったの」
- 家族と食べる晩ごはんの味
- 友達と笑い合った瞬間
- 学校の教室の匂い
「もっとある!!!数えきれない程ある!!!」
「ごめんなさい......私……すごく沢山持ってたんだ......恵まれてたんだ......」
涙ながらにそう言うと、夢の中の存在は静かにうなずいた。
「……気づけたんだね。」この存在は、「守護霊」または「先祖の霊的意識」に極めて近い。
彼女のあまりの無気力に、目を覚まさせるように現れたのだろう。
結び──“平凡”は、失って初めて気づく奇跡
翌朝、彼女は自分として目を覚ました。
記憶は曖昧でも、身体の中に「自分がちゃんといる」感覚があった。
学校に行き、友達に笑いかけた。
授業中、先生の声をしっかり聞き勉強した
特別なことは何もしていない。
でも、今に感謝して、今を大切に生きてる
彼女は、今日も変わらない日常の中で、ほんの少しだけでも前に進もうと「自分で」選びながら生きている。
そのささやかな努力と感謝の積み重ねは彼女の人生を大きく変えていくかもしれない
「私って、本当は何も持ってなかったんじゃなくて……見えてなかっただけだったんだね」
この物語を読んでくれたあなたへ。
もしかしたら、あなたの背後にも、
優しく見守ってくれる“目に見えない存在”がいるのかもしれない。
もし、心がくじけそうになったら──
そのときは思い出して。
- 「平凡という贅沢」
- 「生きていることの奇跡」
それがあるという事だけでも、あなたはとても恵まれている、むしろ何よりの価値を持っているかもしれないと