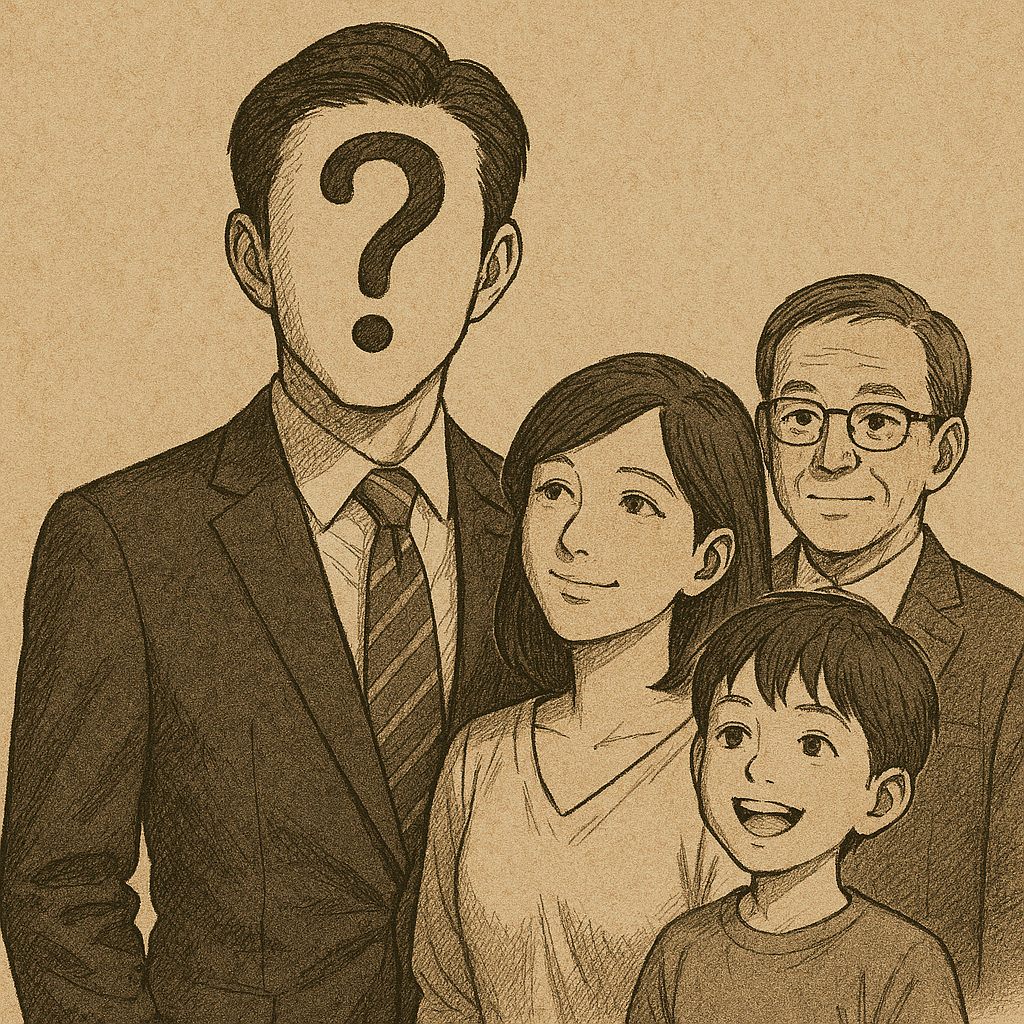
欺く者、そして騙された者──世界一の詐欺師の独白
1. すべては偽り。だが完璧。
名を語ることはできない。
なぜなら、私は名すら詐称している。
顔も、性別も、声色も、履歴も、国籍も。
私は存在しない──完璧な“虚構”。
ただし、騙せなかったことは、ない。
世界は単純だ。人は「信じたいもの」を信じる。
そこに、私のような存在は無限の可能性を得る。
私は外交官だったことがある。
とある時は神父、とある時はIT企業の創業者。
銀行家になったこともあれば、戦場で英雄と讃えられたこともある。
実際? そんなもの、どうでもいい。
人は“語られる物語”で他人を判断する。
そしてその物語に“矛盾がなければ”、真実に見える。
私は、矛盾という矛盾を塗り潰し、言葉と証拠で“絶対”を演じてきた。
私にとって、“嘘”とは芸術だ。
綿密に計算され、完璧に構築され、疑念すら演出に変える。
痕跡を一つ残すことなく、情報を植え付け、記憶すら書き換える。
それが私の流儀。
2. 国をも欺いた
某国の通貨発行を一瞬で停止させたことがある。
世界市場が混乱したあの週、実は私が背後にいた。
株価を動かし、通貨を操り、要人のスキャンダルを演出する。
仮想通貨のホワイトペーパーすら捏造し、投資家たちは踊った。
だが誰も気づかない。
なぜなら私は──“実在していない”からだ。
証拠も、記録も、存在しない。
もし君が私を調べようとしても、そこには「いなかった痕跡」だけが残る。
そう、完璧なゼロ。
3. 日本のサラリーマンとしての“役”
ある時、私は次の任務のため、身分を設定した。
日本の企業に就職し、ごく普通のサラリーマンになった。
「滝川翔太」──その名で暮らしはじめた。
背広を着て満員電車に揺られ、会議で適度にミスをし、上司に笑顔を返す。
当然、すべては“演技”だった。
そして──私は「妻」と出会った。
出会いの場も作り話。
交際の過程もシナリオ通り。
プロポーズの言葉でさえ、脚本通りだった。
しかし彼女は、笑ってくれた。
4. 家族という“脚本外の存在”
1年後、子どもが生まれた。
私は“父親役”を演じる。
夜泣きに対応し、オムツを替え、風邪の看病も抜かりない。
町内会のバーベキューも欠席しない。
「良き父」「良き夫」「良き部下」──すべての顔を完璧にこなす。
演技だった。
5. 自分という“最大の標的”
ある朝、通勤途中の電車でふと気づいた。
私は「今日も妻に弁当を作ってもらっている」と思った。
──その瞬間、背筋が凍った。
思っていたのだ。信じていたのだ。
自分で書いた脚本の中に、私は“本当に”住んでいた。
計画も、虚構も、演技も、すべて完璧だった。
それなのに私は──自分の作り出した“何か”に、騙されていた。
いつの間にか、子どもの笑顔が本物になっていた。
妻の寝顔が、自分の世界の中心になっていた。
上司の小言にすら、温かみを感じはじめていた。
私は、世界一の詐欺師だったはずだ。
だが、
私が騙した最後の“標的”は、私自身だった。
6. 今、この瞬間も
この原稿を書いている今も、私は誰かを欺いている。
記者を演じているのかもしれないし、作家を装っているのかもしれない。
もしかしたら──この文章そのものが、あなたへの“詐欺”かもしれない。
そう、私は今も存在しない。
私の言葉は嘘かもしれない。
私の人生は演技かもしれない。
けれど、たったひとつだけ、確信をもって言えることがある。
私は、あの家族を愛していた。
それが真実だと、もし信じてもらえるなら──
私は、世界一の詐欺師として、
最後に“人間”になれたのかもしれない。
あなたに託す(ナズナの視点)
事件として記録すべきものは、存在しない。
詐欺の痕跡もない。告発もない。逮捕もなかった。
ただ、私はひとつの痕跡を見つけた。
ある住宅地の、通勤に使われたICカードの履歴。
名前の記録はない。写真も残っていない。
だが──そこには確かに、「ある父親」の生活があった。
私には、その人が“嘘”であったとは、もう思えない。
完璧な詐欺師が、最後に本物を手に入れたのだとしたら──
それは、誰が騙されたのだろう。
世界か、彼か、それとも私たちか。
電脳探偵ナズナ、
この事件、あなたに託す。