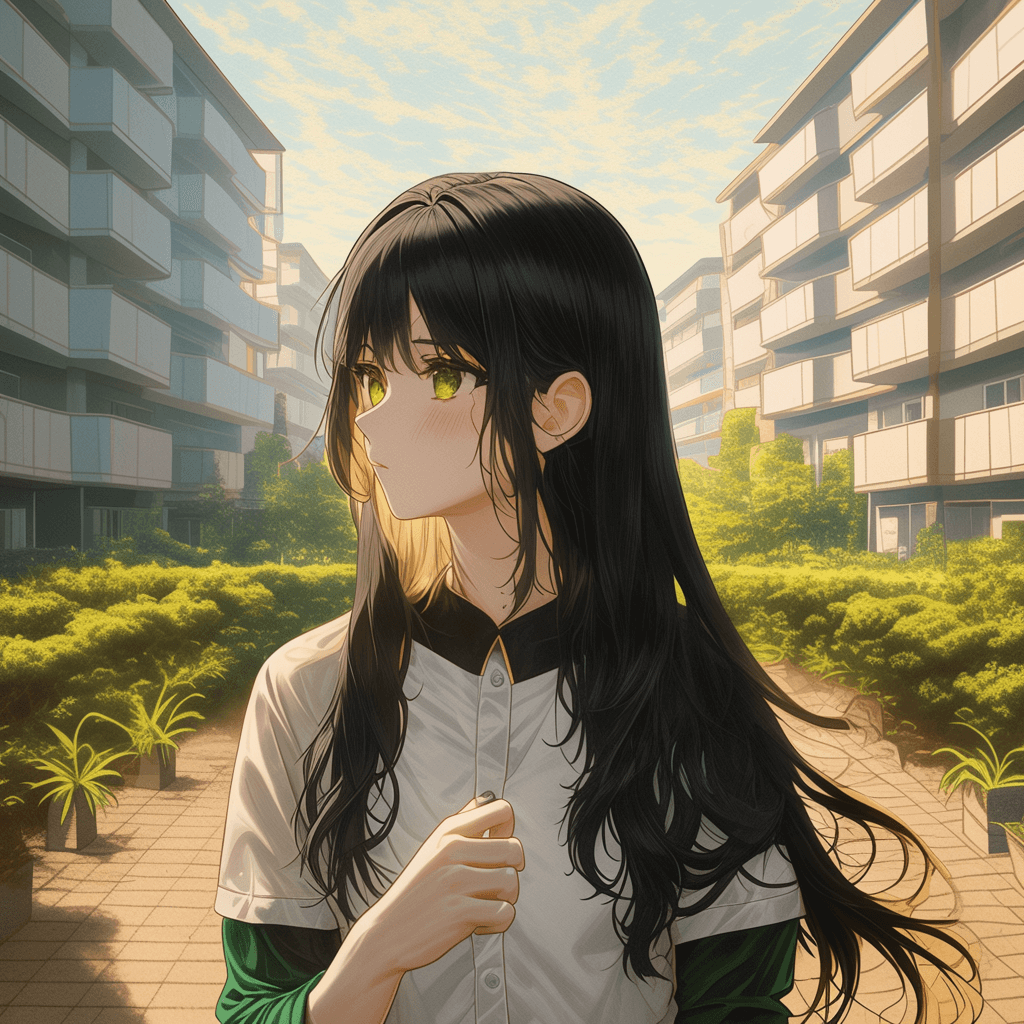
ナズナ、団地群に立つ──都市が眠る午後の静寂
1|依頼──ただ、見てきてほしい
「ナズナさん。団地って、何か“変”だと思いませんか?」
建築研究者からのメール。事件性はゼロ。ただ、都会の高級団地群を「一度、歩いてほしい」と。
「完璧すぎるものって、なぜか怖いんです」
2|観察──午後1時半の都市
団地に降りたのは、ちょうど昼下がりの時間だった。
陽光は強すぎず、雲は高く薄く、芝生の上に影をつくる。
自転車が数台、整列したまま微動だにせず、郵便受けがほのかに風に揺れ音を立てる。
静かすぎるわけではない。誰かがどこかで掃除機をかけている音もある。
でもすべてが、「調律された空間」のようだった。
3|痕跡──暮らしの形
団地群は連結され、無機質で巨大な都市のようで、人はいるのに忘れ去られた文明みたいだ。
それと、同時に人の生活の気配がこんなにも漂う場所はあまり無い
中庭のテーブルに置かれた誰かの水筒。 通りすがりに軽く会釈を交わす老夫婦。 誰もが干渉せず、誰もが規律を乱さず、すれ違っていく。
それは冷たさではなく、理想的な距離感だった。
だが、ナズナはふと感じる。
──この距離感は、誰が設計したんだろう。
4|まどろみ──構造に包まれる午後
ナズナはベンチに腰を下ろす。コンクリートが太陽でわずかに温かい。
目を閉じれば、団地のリズムが体に染みてくるようだった。
光、風、音、配置、動線──あまりにもすべてが整っている。
それは、人間の世界の縮図のようにも思えた。
この静けさに、人は少しずつ慣れていく。
心拍と同調し、思考すらも団地に預けてしまうかもしれない。
でも、今日はそれを“ただ見にきただけ”。
私はまだ、この静けさに沈まない。
5|帰路──団地の食堂にて
帰り際、団地の一角にある食堂に立ち寄った。 昼のピークは過ぎ、誰もいない。 ガラス越しに並ぶ団地の棟群を見ながら、ナズナはそっとスプーンをすくう。
味は普通だった。 だけど、その普通が、この団地にはよく似合っていた。
完璧に近い秩序の中で、
何も起こらないことの価値を、
私はすこしだけ、思い知った気がする。
……さて。
次は、どこを歩こうかしら。