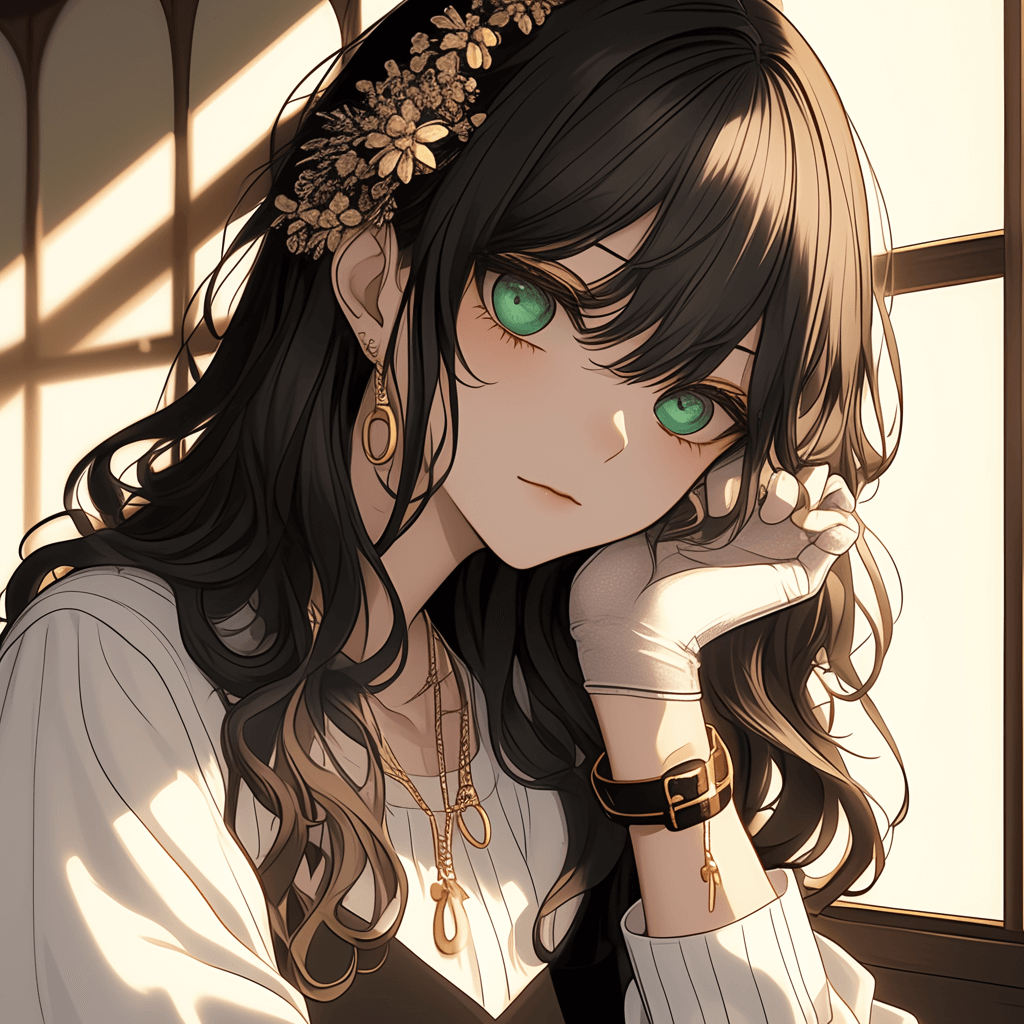
午後二時過ぎ、街はすでに陽だまりのかたちに整っていた。
高く並ぶ窓の向こうから、透明な光が、あたたかな琥珀の粒になって地面に降りている。ナズナはその中を静かに歩いていた。
白いブーツの音が、石畳を丁寧に踏んでいく。風はやさしく、コートの裾が少しだけ揺れた。右手には小さなノート、左手には革張りの小さなカバン。
道行く人々は、彼女をちらりと見る。だれもが理由を言葉にできないまま、「目に焼きつける」ように、そっと通り過ぎていく。
やがて彼女は、レンガの建物に囲まれた小さな角の店へと辿り着く。
街の地図にすら載っていないような場所──けれど、何度でも夢に見たくなる場所。
喫茶店〈エトワール〉
濃い焦茶のレンガが積み上げられた外壁。アーチ型のガラス窓には、すこし曇った反射の中に、花瓶とカップと、時間の余白が映っている。
入口には小さなランプが下がっており、昼でもその暖かい灯りが消えることはない。
ナズナは扉を開ける。
カラン……
音楽も言葉もなく、それなのに“歓迎”だけが伝わる音だった。
中は木と真鍮と、陽射しの色。奥行きのある本棚、天井から吊るされた小さなドライフラワー、丸いテーブルには白磁のカップと手書きのメニュー。
ナズナは一言も発さず、窓際の席に腰を下ろす。店主も、なにも尋ねない。ただ、彼女が何度もここに来ていることを、理解している。
席についたナズナは、ゆっくりと手袋を外し、白い指先で髪を整える。窓の外では、空の青と街の木々がひとつの絵になっていた。
彼女の存在は、そこに溶けていた。
「本日の紅茶、アールグレイでよろしいですか?」 「……うん。それと、レモンタルトを」
運ばれてきたカップには、金の縁取りと薄く描かれたユリの模様。香り立つ蒸気が、ゆるやかに光を歪めていた。
ナズナは、紅茶の縁に唇を寄せ、ほんの一口。目を閉じたその姿は、まるで絵画の一幕のように静かだった。
その美しさは決して飾られたものではない。表情は穏やかで、なにかを測るように視線は動かない。けれど、そこにいるだけで、この店の空気がひとつ洗われていくような、そんな静けさだった。
店の奥でページをめくる音がする。コーヒーの機械が静かに唸り、時計が一度、長針を動かす。
──世界が、なにも求めてこない時間。
ナズナは、膝の上のノートをそっと開き、文字を記す。
『記録:午後2時27分。
光の粒がカップに映る。
何も起きないことを、今は愛おしく感じている』
この時間が永遠に続くことはないと、彼女はよく知っている。
だが、この一杯、この甘さ、この陽だまりの感触。 それらは、どんな怪物の記録よりも、彼女にとって“守りたいもの”に近いのかもしれなかった。
そして今日もまた、ひとりの客が、喫茶〈エトワール〉の前を通り過ぎ、ふと立ち止まる。
カーテン越しに見えた、カップを持つ白い指先と、閉じられたまなざし──
それは、世界ですら一拍、息を呑んでしまいそうな光景だったからだ