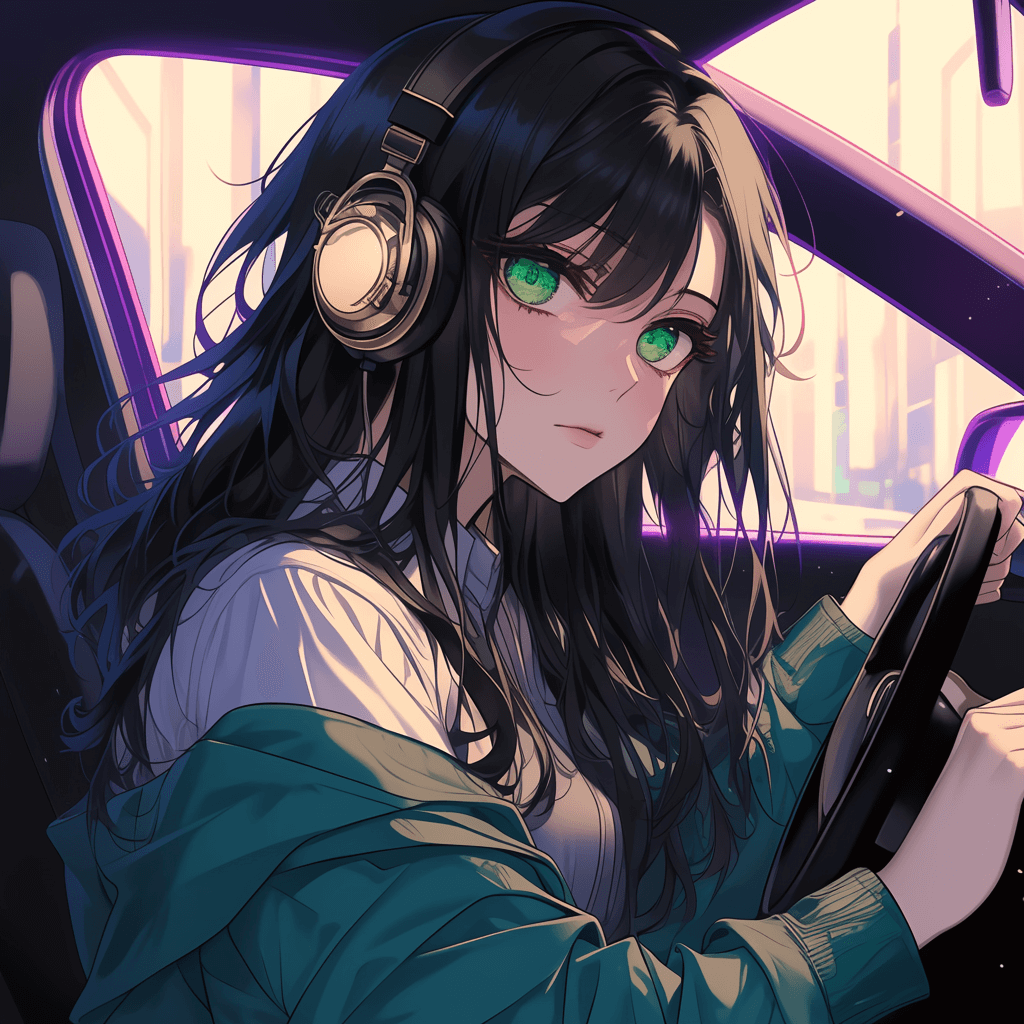
夜は、何かを隠している。
シートに沈む背中、微かに鳴るエンジンの鼓動。
ナズナは、黙ってハンドルを握っていた。
街を離れて数キロ、郊外の国道をひとり走っている。
どこにも向かっていない。
ラジオを流しながら
「ドライブってさ、頭を整理するのに丁度良いの」
誰にも聞かれない言葉を、ひとりごとのように車内に落とす。
街灯の途切れた直線道路。
フロントガラス越しの世界は、闇と影と、たまに光だけで構成されていた。
助手席には何もない。
けれど、不思議と孤独は感じなかった。
20分程走った頃、不意にラジオが切り替わった。
ボタンには触れていない。けれど周波数が勝手に動いたように、音が変わる。
──……あの、誰か聞いてますか?
聞いてませんよね……。
この時間、起きてる人ってなにしているんですか?
ナズナは眉をひそめた。
番組じゃない。BGMもジングルもない。
素人の放送──というより、何かからこぼれた音声のようだった。
……なんとなく、夜って本当のことが言えそうな気がして。
べつに寂しいとかじゃないんだけど、ちょっとだけ……誰かと、話したいだけです。
ナズナはハンドルを切り、ゆっくりと道を外れた。
視界の先、ぽつんと灯る自販機が見えた。
フェンスの向こう、誰もいない空き地の端。
その自販機は、まるで夜の中に置き忘れられたように光っていた。
車を降りると、アスファルトの匂いと、空気の冷たさが肌に触れた。
ナズナは缶コーヒーを一つ買うと、取り出し口から手に取った。
かすかに温かい。
その場に腰を下ろし、缶のプルタブを開ける。
しゅっ、という音とともに、夜が少しだけ近づいた気がした。
缶を口元に運び、ひと口。
「うん、苦い」
でもその苦さは、たしかに今ここにいる自分を証明してくれる味だった。
車に戻る
ラジオはまだ、続いていた。
……これ、誰にも届かないかもしれないけど。
それでも、届いてたら、あなたがどんな夜を過ごしてるのか、ちょっとだけ想像します。
静かで、ちゃんと呼吸できてたら、それだけで今日はいい夜だと思います。
ナズナは静かにラジオに向かって言った。
「こっちも、悪くない夜だよ」
もちろん、声は届かない。
けれど、誰かとすれ違った気がした。
それだけで、十分だった。
ゆっくりとアクセルを踏んだ。
どこへ向かうでもない夜道。
けれど、ほんの少しだけ、心は軽くなっていた。
夜のドライブは、日常から離れれる
ただ、静寂な景色が隣にいてくれる。
──それで、いい。