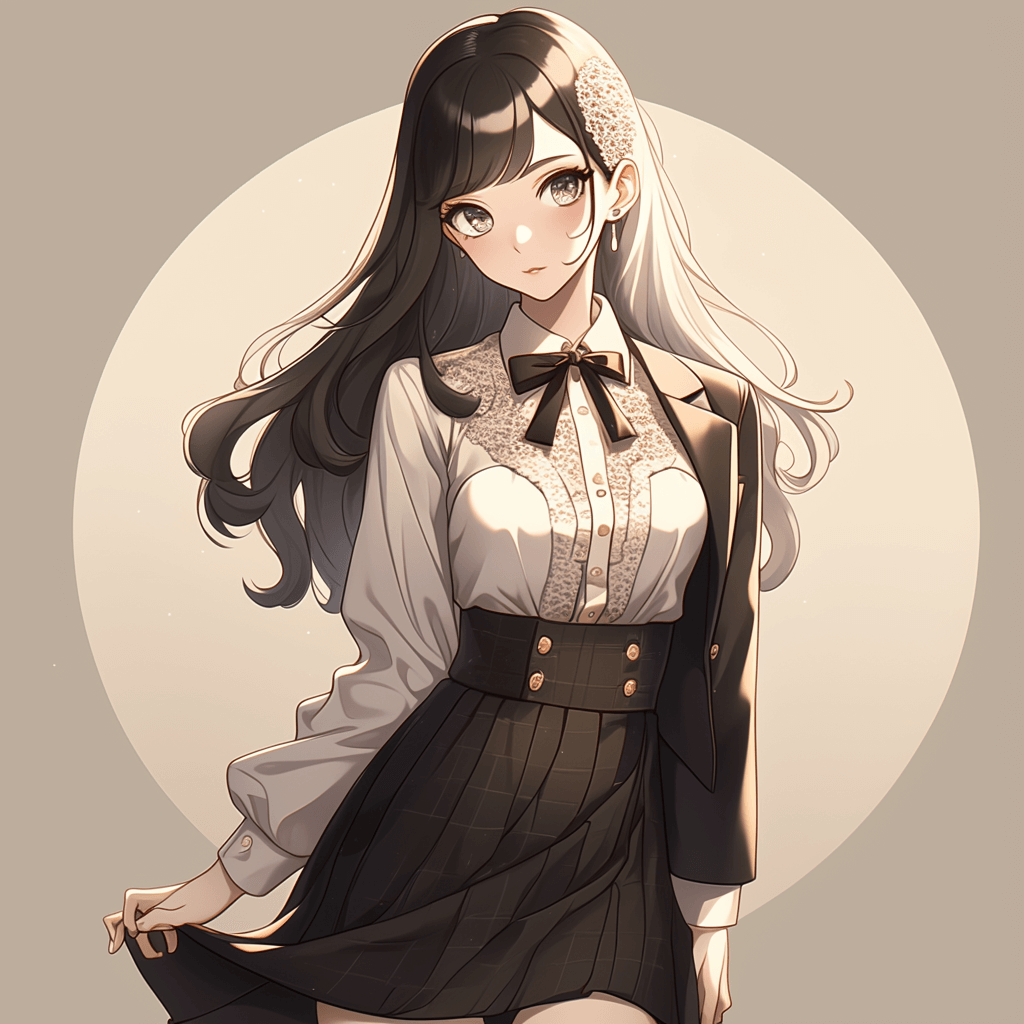
ナズナ過去編 花芽 瑠璃 について
第一章:微かな違和感
教室という場所は、不思議な秩序で成り立っている。ざわついているようで、均衡が保たれていて、誰かが声を上げれば、それに応じる誰かが自然と現れる。そのなかで、ナズナはただ静かに、外の空を見ていた。
高校二年の春。季節はすでに落ち着き、窓から吹く風はどこか初夏の香りを含んでいた。ナズナは教室の一番後ろ、窓際の席に座っていた。例によって誰とも話さず、ただ観察するように過ごしていた。
その日、ナズナが初めて違和感を覚えたのは、昼休みが終わる直前だった。
「……あれ? ペンケース、どこやったっけ……?」
前の席の女子が、首をかしげながらカバンを探っている。少しざわつきが広がるが、すぐに別の話題にかき消された。彼女は仕方なく、友達にペンを借りて授業を受け始める。
そのときは、ナズナも深く考えなかった。物がなくなるなんて、誰にでもあることだと思っていたから。
だが、それは始まりにすぎなかった。
数日後──今度は別の生徒が「髪留め、落としたかな……?」と呟いた。その翌週には、また違う生徒が「ピアス、片方だけ無くなってるんだけど」と言っていた。どれも騒がれることはなく、先生も取り合わなかった。なぜなら、どれも“取るほど価値がある物”ではなかったから。
だが私は、そこに小さな「選び」の傾向を感じていた。
なくなっているのは、いつも、教室の中で目立つ子たちの持ち物だった。声が大きく、グループの中心にいて、無意識に周囲を支配しているような。誰かを見下す言葉を平気で使いながら、それを「冗談だよ」と笑って済ませるような──そんな生徒たちの物だけが、奇妙に“消えていた”。
私は思った。
──これは偶然じゃない。
誰かの意図が垣間見える......
花芽 瑠璃(カガ メ ルリ)。
物静かで、控えめで、誰かに強く関わることのない、優しい子。授業中も目立たず、グループにも属さず、それでも孤立はしていなかった。誰もが彼女に対して「いい子だ」と言う。ナズナも、そう思っている。いや──それ以上に、彼女のことを“自分と似ている”と感じていた。
第二章:その目が見ていたもの
ナズナが彼女に一目置いていたのは。教室の中で、声を出す回数が少ないにもかかわらず、彼女の存在は妙に印象に残るからだった。それはたぶん、彼女の“視線”のせいだ。
花芽 瑠璃(カガ メ ルリ)は、誰かと話しているとき、決して真正面から目を合わせない。かといって、目を逸らしているわけでもない。あえて“少しずれた角度”から、まるで相手の輪郭をなぞるように、柔らかく見ている。
ナズナはそれを見たとき──直感的に、「この人は、“見えすぎる”んだな」と思った。
見えすぎる人は、距離を取る。誰かの痛みや本音や悪意が、視界に入りすぎるから。そして、そういう人は、優しさを守るために、ある日そっと境界線を引く。
観察を続ける中で、ナズナはいくつもの“確信”を得た。
たとえば、昼休みに友達グループの誰かが席を立った直後。瑠璃はそっと立ち上がり、彼女の机の引き出しに手を伸ばす。中に何があったのか、ナズナには見えなかった。だが、彼女はその手をすぐにポケットに入れて、何事もなかったように振る舞った。
あるいは、掃除の時間。みんながふざけてほうきを振り回している中、瑠璃は静かにひとりでモップをかけていた。そのあと、ちょっとした“失くし物”がまた1つ、消えた。
だけど──彼女は誰のことも傷つけようとはしていなかった。それは、彼女の姿勢から、表情からなんとなく感じ取れた。
あるとき、ナズナはみた。グループの中心にいる生徒たちが、休み時間に誰かの悪口を言っていた。「なんか瑠璃って、ちょっと変じゃない?いつもひとりでさー」「うんうん。目合わせてくれないし、なんか“感じ悪い”って言ってた子もいたよ」
それを瑠璃は、何でもないような顔で聞いていた。ロッカーに教科書を取りに行くふりをして。背中を向けていたけれど、ナズナは知っていた。あのときの彼女の手が、震えていたことを。
それでも──彼女は誰にも何も言わず、翌日にはまた笑顔で「おはようございます」と小さく挨拶していた。
ああ、やっぱり似ている。ナズナは、心の中でそう呟いた。この子は、自分と同じ種類の人間だ。誰にも触れられないように距離を取りながら、それでもどこかで“関わりたい”と願っている。
だからこそ、ナズナは迷った。
このまま、何も知らないふりをすることもできた。“告発”すれば、彼女は孤立するだろう。でも、許してしまえば、それは──彼女の中に残る“優しさ”すら、壊してしまうかもしれない。
私は、机に手を置き、静かに目を閉じた。
彼女が“間違えた”のなら、誰かがそれをそっと、正してあげなければならない。でもそれは、怒りや糾弾でなくていい。この子が本来持っている優しさを、もう一度信じる形で──
自分にできることは、ひとつだけだった。
ナズナは、その夜、自宅で便箋を取り出した。筆圧を調整しながら、何度も書いては破ってを繰り返し、ようやく短い文章をひとことだけ──
「知ってるよ。でも、あなたはまだ、やり直せると思う。」
第三章:やり直せる余白
翌朝、ナズナは少しだけ早く登校した。昇降口にはまだ誰もいなくて、湿った春の空気が静かに漂っていた。靴箱の中に、そっと手紙を差し込む。瑠璃の名前が書かれた小さな木札の下──誰にも気づかれないように。
たった一行の言葉。
「知ってるよ。でも、あなたはまだ、やり直せると思う。」
名前は書かなかった。けれど、彼女にはわかるはずだった。あれだけ世界を見ている人なら。あれだけ、沈黙の中で人の真意を読み取ることができる人なら。
それからの数日は、特に何も起きなかった。瑠璃も、いつもと変わらずに静かに席につき、静かに授業を受けていた。盗難の話も、すでに生徒たちの記憶から薄れつつあった。
だけど、ナズナは知っていた。彼女の歩き方が、ほんの少しだけ重たくなっていたこと。ノートを取る指が、以前より少しだけ慎重になっていたこと。手紙を受け取ったその日から、彼女の呼吸が、何度か乱れていたこと。
そして──数日後の昼休み。
「先生、あの……ちょっとお話したいことがあって」
彼女がそう言って、担任の席に向かったとき、私は教室の端で、手を止めて彼女を見送った。
その表情には、恐れも、不安も、なかった。
あったのは、たぶん──決意だった。
後で聞いた話では、彼女は先生に全てを話したという。盗んだものの在り処と、その理由。最大限のお詫びの言葉で締めくくられたらしい。
先生も騒がなかった。生徒指導にもならなかった。物が戻され、関係者にだけ静かに伝えられ、それで終わった。
第四章:静かな祈り
それから数日後の放課後、ナズナは図書室にいた。いつもの席で、誰も借りない古い詩集をめくっていたときだった。
気配に気づいて顔を上げると、そこに彼女が立っていた。
花芽 瑠璃(カガ メ ルリ)。制服の襟は整っていて、髪も丁寧に揃えられていた。彼女は何も言わず、ただ一歩、ナズナの机の前まで進んだ。
そして──深く、深く、頭を下げた。
ナズナに向けて、でも何かを求めるわけではなく、言葉では言い表せない、まるで“祈り”のような礼だった。
それで、すべては終わった。
彼女とは、その後、話すことも、関わることもなかった。少しだけ寂しい気持ちがあったのを覚えている。彼女となら仲良くなれた気がしたから。
終章:正義じゃないもの
あのとき私は、“正しさ”ではなく、“信じること”を選んだ。
人は、他人の間違いを見つけると、それを指摘したくなる。
それが“正義”だからではなく、むしろ、心のどこかにある怒りや不満や、誰かを下に見ることで自分を保つための──そんな感情の発散であることが多い。
けれど、その発散は、未来をつくることとは別だ。
間違いを指摘することと、その人が“やり直せる場所”を残すことは、まったく違う。
それは、すべての人に当てはまるものではない。けれど──
瑠璃のように、他人を思い、心を削って、それでも間違えてしまった“善き人の過ち”には、きっと誰かが“その後”を示してあげる必要があるのだと思う。
だから私は、あのとき、彼女を裁くことよりも、信じるという選択をした。
花芽 瑠璃。私はなんとなく彼女が好きだった。気高い花の様で.....