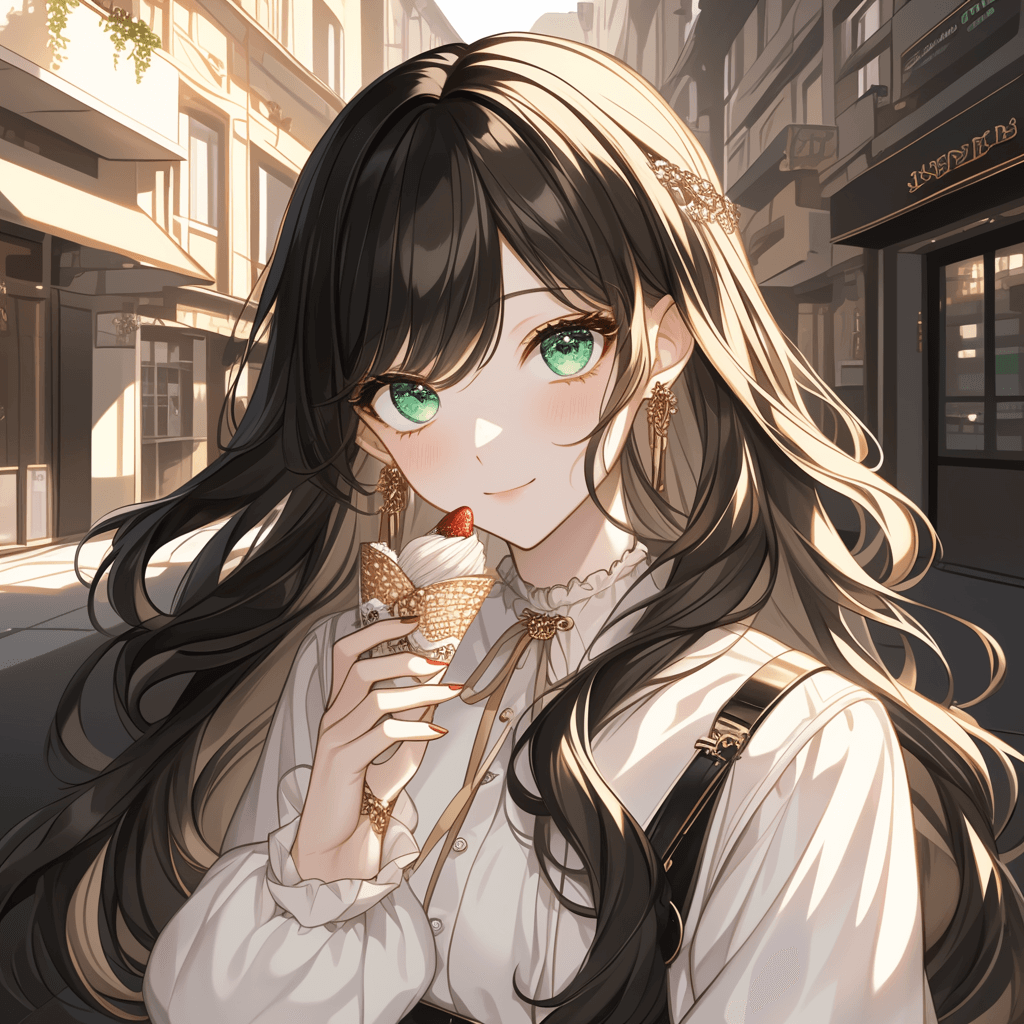
彼女は、笑っていなくなった
──わたしと、友達になってください。
そのメールは、いつものように端末に届いていた。
ただ、その一文の件名だけがぽつりと不安そうに画面に浮かんでいた。
ナズナはしばらく、画面を見つめた。
依頼文としてはあまりにも曖昧で、情報も少ない。
でも、そこにはどこか切実さがあって──
ナズナは、自然と返信ボタンに手を伸ばしていた。
差出人は「夕凪ことり」、16歳。
理由は特にないけれど、どうしても誰かと話がしたい。
人と関われないまま毎日を過ごしていて、声をかけてくれる人もいない。
でも、ナズナさんなら──という、短い理由が添えられていた。
ナズナは迷った。
人と話すことができない。外に出られない。
依頼というには曖昧すぎるし、責任が伴い短期で解決できる“事件”でもない。
けれど、どうしてだろう──ナズナの中で、なにかが動いた。
「友達」という言葉。
それは、ナズナにとっても、まだ少し距離のある響きだった。
指定された住所は、町の外れにある、ごく普通の綺麗な一軒家
時刻は午後二時。ナズナは、彼女の家の前で立ち止まった。
「……ナズナです。電脳探偵──と呼ばれてる者です」
声をかけると、数秒の沈黙のあと、扉がゆっくりと開いた。
そこには、長い黒髪を揃えて下ろした、小柄な少女がいた。
制服ではない、ゆるめのパーカーとスカート。
顔色はあまりよくなかったが、瞳だけはまっすぐ、私を見ていた。
「……ほんとに、来てくれたんですね」
彼女は、ふっと微笑んだ。
その笑みは、どこか夢みたいに儚くて──
ナズナは、そのとき、ほんの少しだけ、心を奪われた気がした。
「夕凪ことりさん、だね。改めて……よろしく」
「はい。……あの、わたし、うまく話せないと思うけど……でも、がんばってみます」
ナズナは頷いて、部屋の中へと足を踏み入れた。
ぬいぐるみと本と、窓のカーテンが淡いブルーだった。
そしてこの日から、彼女との日々が──始まった。
--------------------------------------------------最初の数日は、ほとんど会話にならなかった。
ことりは小さな声でぽつりぽつりと答えるだけで、目を合わせることすらできなかった。
ナズナは無理に話しかけることはせず、彼女のペースに合わせて、静かに過ごすことにした。
たとえば──本棚を一緒に眺め、漫画や小説のおすすめ作品の話をしたり
彼女の好きな詩集を手にとって、言葉のリズムについて話したり
ときどき、ナズナは店で飲んでいる紅茶を持っていき、ふたりでそれをゆっくり味わった。
「この紅茶……ナズナさんがいつも飲んでるやつですか?」
「うん。香りが落ち着くから、私はこれが好き」
「……わたし、紅茶って苦手だったんですけど……これは、ちょっとだけ、好きかも」
そんな小さな“共有”が、ことりの表情を少しずつ変えていった。
一週間ほど経った頃、彼女が初めて、自分から「外に出てみたい」と言った。
「人がいない時間なら……あの、ちっちゃな公園とか、なら……」
「じゃあ、明日の午後、行ってみようか」
翌日、ことりは白い帽子をかぶって、少しだけ緊張した面持ちでナズナの前に現れた。
「変じゃないですか……?」
「似合ってるよ」
「……ありがとうございます」
公園のベンチにふたり並んで座る。
「ナズナさんって、どうしてそんなに静かなんですか?」
「うるさいより、いいでしょ」
「……うん、でも、なんか……ずっと隣にいてくれる感じがして、落ち着く」
ナズナは、ことりの横顔を見た。
初めて会ったときと違って、彼女の輪郭はどこか柔らかくなっていた。
「わたしね、昔から、“いない方がいい子”って思われてる気がしてて……」
「……」
「でも、ナズナさんが来てから、なんか……ちゃんとここに居てもいいんだって、思えるようになったんです」
ナズナは、すぐに返す言葉が見つからなかった。
ただ、静かに頷いた。
その日から、彼女は日記のような小さなノートをナズナに見せてくれるようになった。
ページには、ナズナとのやりとりや、嬉しかった瞬間、緊張したけど勇気を出せたことが丁寧に書かれていた。
──そこには、確かに“彼女自身”の言葉が息づいていた。
ある日、ふたりで夕方の喫茶店に入ったとき、ことりが言った。
「ナズナさんが、最初からずっと“私の友達”でいてくれたら、よかったのにな」
「最初から?」
「……ううん、今でもいいんです。これからも、ナズナさんがずっとそばにいてくれたら……」
ナズナは、胸の奥に小さな違和感が生まれたことに気づいた
けれどそのときはまだ、それを“決めつける”事は、彼女の無邪気な笑顔を見ると出来なかった
ことりの変化は、嬉しいものばかりではなかった。
彼女は又、社会との関わりを避けるようになっていった。
「学校は、やっぱり怖いんです。
だって、誰も私のこと見てくれないし……みんな、目を合わせないようにしてくる」
「でも、ナズナさんは違う。ちゃんと私のことを見てくれる。
だから、もう……他の人はいらないかなって思って」
その言葉に、ナズナは、はっきりとした違和感を感じた。
彼女の視界の中から、世界が消えていくような言葉。
ナズナだけが、彼女の世界の“全て”になってしまっている──
それは、真の意味でことりを救う方法とは逆だ。
だからナズナはタイミングを見計らって、彼女に静かに話しかけた。
「ことり。……君は、もうひとりでも大丈夫なはずだよ」
「え……?」
「最初に会ったときの君とは違う。外にも出られた。言葉もちゃんと話せる、自分の気持ちも人に伝えられた。
それって、君がひとりで歩こうと頑張ったから出来たこと。私がいたからだけじゃない。君の力だけでもきっとできるよ」
ことりの笑顔が、ゆっくりと、消えていった。
「……どういうこと.....ですか?」
「君なら、学校にもちゃんと通える。もっと他の人とも関われる。
私とじゃなくても、君の居場所は、世界の中にちゃんとある」
──ナズナは、彼女の背中を押したつもりだった。
けれど、それは、彼女にとっては“拒絶”にしか感じられなかったのだ。
「……そっか」
彼女の声が震える。
「じゃあ……最初からそうだったんですね」
「ことり……?」
「やっぱり……依頼だから来てくれたんですよね......
最初から今まで仕事だったんですよね……」
私は、言葉を失った。
「……大嫌いです!!!
もう、二度とかかわらないでください!!!」
「……ことり、それは──」
「帰ってください!お願い……っ、帰って……!!!」
彼女の大量の涙と怒りと悲しみの混じった悲痛な叫びに、ナズナはそれ以上何も言えなかった。
玄関に向かい、扉を静かに閉める。
部屋の中から、今までで一番大きなことりの声が聞こえた。それは泣き声がだった。
心底胸が締め付けられた........でも、その声に応える事はしなかった。
------------------------------------------------
あれから、ことりとは一度も会っていない。
その後、彼女が転校したと、ある情報筋で聞いた。
新しい場所で、新しい日々を始めたのかもしれない.....それはナズナの願いでもあった
彼女のノートは、ナズナの手元に残されていた。返し忘れていたのだ
ふと、最後のページに何かが書かれている事にナズナは気づいた。そこには震えた字で、こう書かれていた。
「ナズナさん.......こんな私だから......いつか困らせる日が来ると思います.......先に謝っておきます、ごめんなさい.......。その時私が何を言おうと......ホントの気持ちはこうです.....あなたが私に光をくれた時から......生きる事はこんなにも楽しいって知りました.......ずっと大好きです」
ナズナは今でも、ときどき考える。
あのとき、どうすればよかったのか。
優しくすること、突き放すこと、どちらが正解だったのか──
けれど、答えは出ないまま、時だけが静かに流れていく
紅茶の湯気が立ちのぼる窓辺で、私は今日も思い出す。
──あの子と初めて心が通じ合った日のことを........