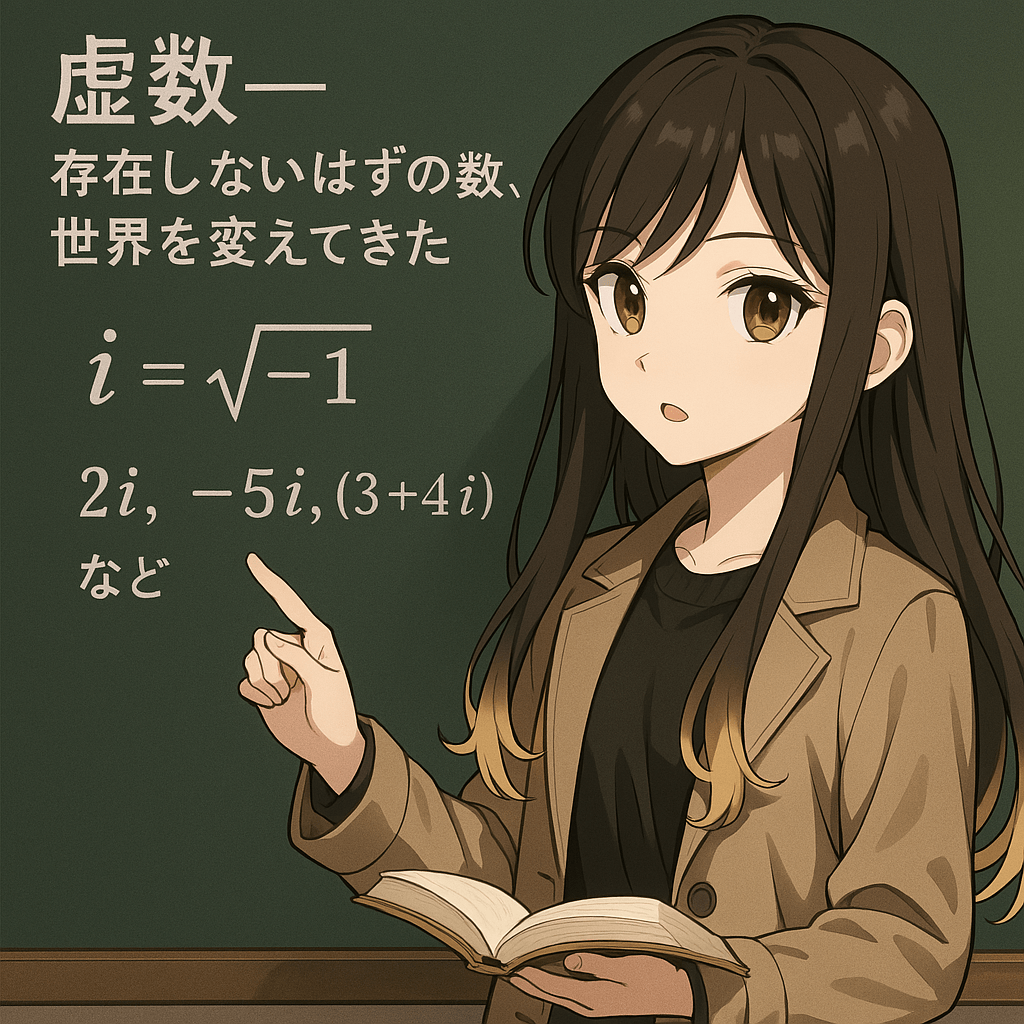
虚数──存在しないはずの数が、世界を変えてきた
1. 事件
「それは存在しない数です。でも、なぜか現実に効いている」
その言葉を聞いた瞬間、私は立ち止まった。依頼者は高校で数学を教える教員だった。ある日、生徒にこう聞かれたという──「√−1って、なんで存在しないのに使うの?」
一瞬、答えに詰まった彼は私のもとを訪れた。
「虚数って……“ある”んでしょうか?」
私は静かに頷いた。そして、こう言った。
「虚数は、確かに“この世界のどこにもない”。でも──“この世界を動かしている”」
ナズナ、調査開始。
2. データ収集
■ √ の誕生
数学における「√」は、“どの数を2乗すればこの数になるか?”を逆にたどるための記号だった。
例:
- √4 = 2(2² = 4)
- √9 = 3(3² = 9)
つまり、√a × √a = a。
だがこの「√」には前提がある。中身(ルートの中)は、0以上であること。なぜなら、どんな実数を2乗しても、負の数にはならないからだ。
- 正 × 正 = 正
- 負 × 負 = 正
だから、x² = −1 のような方程式には、実数では“答えが存在しない”。
■ 数学の進化と限界
17世紀、数学者たちは二次方程式を使って未知の数を求めようとしていた。だが、あるとき式の途中で √−1 が現れてしまう。それは明らかに実数ではない。
最初は「無意味な記号」とされた。だが、結果としては正しい答えが得られる。
「意味は分からない。でも、答えは合っている」
それが、虚数のはじまりだった。
■ 虚数の定義
やがて、数学者たちはある決断を下した。
「√−1 に“名前”を与えよう」
こうして生まれたのが、虚数単位 i(アイ):
i = √−1この定義により、以下のような数が存在可能になる:
- i² = −1
- 2i, −5i, (3 + 4i) など
これらを「虚数」または「複素数」と呼ぶ。
■ 複素数平面と対称性
虚数の登場は、“数の世界にもう一つの次元”を与えた。
実数は1本の直線(数直線)上にある。虚数は、その直線に対して直角方向に広がる「新しい軸」を作った。
- 横軸:実数(Re)
- 縦軸:虚数(Im)
この「複素平面」は、数に回転や振幅といった“動き”を与える。現実世界の現象──電波、音、光、量子の振る舞い──において不可欠な数学的構造になっていく。
■ 虚数の応用
現代では、虚数は以下のような分野で欠かせない:
- 電気工学(交流回路の計算)
- 量子力学(シュレーディンガー方程式)
- 振動解析、信号処理(フーリエ変換)
- 制御理論(伝達関数)
つまり、「現実の中では“存在しない”数が、現実を最も正確に記述している」
3. 推理
ここで、私は根本的な疑問に立ち返った。
「なぜ虚数は必要だったのか?」
それは、「正の平方根だけでは“対称性”が失われるから」である。
たとえば、9 には ±3 という2つの平方根がある。だが「√9」と記述した場合、数学では“正の方だけ”を選ぶ。これは、計算を一意に定めるためのルールだ。
しかし、ある時点で「√−1」のような負の数が現れた。それまでのルールでは、扱えない。
だが、正の平方根だけを認めておいて、負の平方根を排除するのはおかしい。数の世界は“対称であるべき”という美学がそこにあった。
「存在しないのではない。見えないところに、もう一つの軸があるのではないか?」
これが虚数軸の誕生につながった。
つまり──虚数とは、「正と負の対称性を、数の世界に回復させるために生まれた」存在なのだ。
4. 仮説
■ 仮説①:虚数は“数の影”である
虚数は、目に見える量を持たない。だが、その存在は実数と共鳴し、現実世界のあらゆる現象に現れる。
それはまるで、“正の数が光なら、虚数は影”のようだ。
■ 仮説②:虚数は“現実を写すために必要な鏡”
現実世界の波や振動、粒子の運動、情報の流れは、虚数を含む数で記述すると最も美しく、簡潔になる。
つまり虚数とは、我々の世界を正確に記述するために必要な“数の鏡面”である。
■ 仮説③:虚数は「√」という記号の限界から生まれた
√は正の平方根を選ぶ記号であり、それは計算の一意性を保つための“制限”であった。だが、√−1という式が現れたとき、その制限は破綻する。
このとき、「新たな記号(i)」を創造し、“見えない数”を受け入れた。
虚数は、√の限界を超えたことで生まれた「もう一つの√の世界」の住人だったのだ。
5. あなたに託す(ナズナの語り)
あなたが √9 を見たとき、それが“+3”であることに疑問を持ったことがあるだろうか。なぜ −3 ではいけなかったのか。なぜ正だけを選んだのか。
そこに「数を一意にしたい」という数学の願いがあった。
だが、その願いの中から、「選ばれなかった側」が生まれた。
そして私たちは、負の数にも帰る道を作る必要に迫られた。
それが虚数。
見えないけれど、確かに存在し、現実を記述する“影の軸”。
虚数は、「実在しない」ことによって、最も深くこの世界に関わっている。
私たちの現実は、おそらく片面にすぎない。
数の世界は、あなたが思うより、ずっと深い。
その深淵の入り口に、i は静かに待っている。