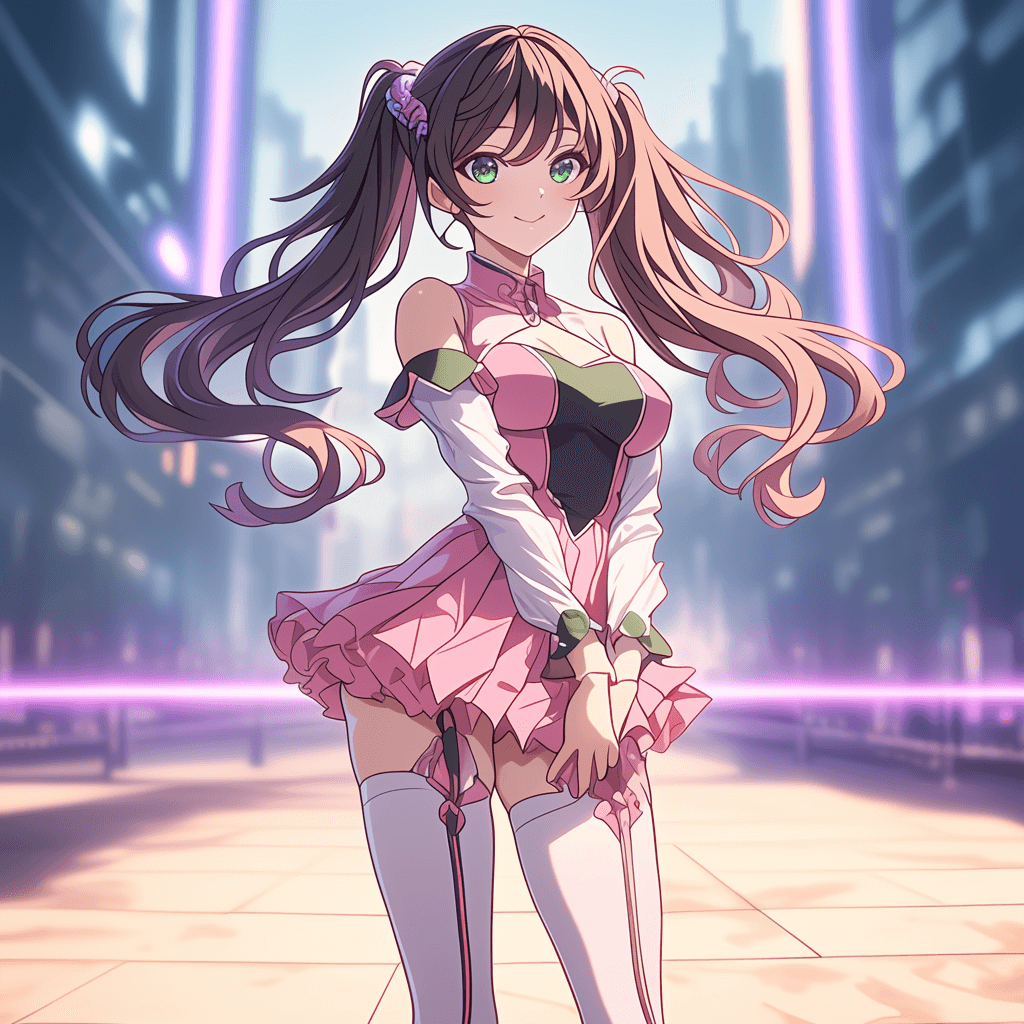
街を駆ける魔法少女
夜の街を駆け抜ける風のように、ナズナは走っていた。
薄いピンクのスカートが夜風にふわりと舞い、胸元のリボンが揺れる。
肌に触れる空気すら少しこそばゆくて、いつもと違う感覚に心がざわめく。何より、体や顔も、いつものナズナより7歳ぐらい幼い
「……まったく、なんで私がこんな格好に……」
スカートの裾を押さえながら、ナズナは頬を赤く染めて呟いた。
普段着慣れた私服とは明らかに違う。
短くヒラヒラとしたスカートの下では、膝上まで伸びた白のニーソックス。
胸元には、星を模した装飾がまるで呼吸のたびに小さく跳ねるようだった。
「風が……スカートの中に……きゃっ……ちょ、ちょっと……見えてないよね……?」
ナズナは自分の姿に耐えかねて、電柱の陰に隠れてうずくまった。
どこかで物陰から誰かに見られている気がして、身体をすぼめる。
彼女にはわかっていた。この姿の始まりが――数日前、突然の“来訪者”によってもたらされたことを。
回想:部屋に現れた少女
「泊めて。今すぐ。……それとも、あなた、王女を外で野宿させる気?」
その夜、ナズナの部屋に突然現れた少女は、白銀の髪に透き通るような肌、そして堂々とした態度を持っていた。
名前は……「アウリサ」と名乗っていた。
「あのー……どちら様??部屋間違ってると思うんだけど?迷子なのかな??」
「馬鹿にしないで!!ナズナちゃんに会いに来たって言ってるでしょ!!私、ここまでの移動の魔力消費でクタクタなの!紅茶、ある?ちょーだい。冷たいの、ミルクは入れてね」
当然のように部屋に上がり込んで座布団に腰を下ろし、足を組むその仕草すらどこか様になっている。
ふわりと香るのは月光に晒されたような香水の気配。まるで、この世の存在じゃないみたい。
「うそでしょ……また、こんな......絶対に厄介な事起こるじゃん......王女って言ってるし」
ドア越しの魔導術
「だ、だめっ、だめだよっこの世界にはね、プライバシーってのがあって、人の部屋には勝手に入っちゃダメなんだよ!!?」
ナズナはアウリサを押し出し、バタバタと慌ててドアを閉め、内側から鍵をかけた。
「ふぅ……危なかった.......何かに巻き込まれる空気しかしなかった......」
そのとき、静かに聞こえてきた声。
「……うぅ……ナズナちゃん……ごめんね……でもね、知らない場所で......ひとりって……怖いの……」
すすり泣くような声。まるで夜風に濡れた子猫みたいに、弱々しくて、放っておけなかった。
「……っ、うそ泣きでしょ……でも……ほんとに泣いてる?可哀そうかも……ちょっとだけ、様子見るだけ……」
ナズナがそっと扉を開けた瞬間だった。
「ふふ、やっと開けた」
ぱあっと白い光が広がる。魔法陣のようなものが床に現れ、風が巻き起こった。
「えっ、な、なにこれ!?うわっ!?!?……わああああっ!!?」
身体が宙に持ち上がり、全身を何か柔らかいものが包み込む。
布地が肌を撫で、フリルが浮かび、光が弾けて――
目を開けたとき、ナズナはまるで魔法少女のような姿になっていた。
ピンクのスカート、肩をわずかに露出させる白いブラウス、胸元には小さなリボンと魔導宝石。おまけに顔と体が7歳ぐらい若返ってしまってる
「な、なにこれ!?!?!?!?!?!?!」
頬を真っ赤にし、ナズナは全身を隠すように身を縮める。
スカートの裾を必死に押さえながら、アウリサを睨む。
「こ、こんなの絶対に変態の服じゃない!!!それに体、こんな子供みたいな体じゃ依頼受けられないじゃない!!」
アウリサはケラケラと笑う。
「でも似合ってるわよ?まさに魔法少女って感じ! ふふ、ちゃんと魔力も通してあげたから、使い方次第では空も飛べるわよ?」
「そ、そんなのいらないしっ!!!ねーーお願い!戻してっ.....いや、戻してください」
「わかったわよ、せっかく可愛いのに勿体ない。その代わり私が満足するまで、おうちに泊めてくれないと戻さないから」
ナズナは背に腹は変えられなかった。いきなり魔法少女?冗談じゃない恥ずかしすぎる!!私は知能を駆使して論理で解決する探偵だ!!
「はい.....でも、あの贅沢とかはできないですけど.......大丈夫ですか.....王女様?」
「アウリサでいいわっ....我慢するしかないわね!それぐらい常識はあるわ!ところで紅茶まだ??」
ナズナが最も苦手とする、人とずっと一緒に居る、プライバシーが無い、その状況が今ここに幕を開けた。彼女にとって最大の試練かもしれない
始まる奇妙な同居生活
その日から、ナズナとアウリサの奇妙な同居生活が始まった。
朝、目を覚ますとすでに隣に人の気配がある。
「ナズナちゃん、おはよう。今日は私、夢の中でドラゴン倒してたよ。褒めて」
「えっ……何言ってるの、まだ眠いってば……依頼まで眠らせて...ってうわ、なんで布団に二人!?」
ナズナが必死に布団を分けようとしても、アウリサは器用に絡みついてくる。
「くっついてる方が、魔力の循環が効率的なの。ね、理にかなってるでしょ?」
「いや魔力以前に、パーソナルスペースが無いと私ダメなんだよーー....って又、寝てるし。人の布団の中でスヤスヤしないでよーー」
洗面所も台所も、すべてがアウリサの“王女流”で彩られていく。
「トーストは耳を切り落として、王族用のジャムを塗るのが礼儀よ」
「こらっ勿体ないよ!? てかそのジャムどこから出した!?」
お風呂でも、事件は絶えない。
「わたしのバスタイムは月光を浴びながらが基本よ」
「いや、窓開けたら寒いし!近所に見られるし!あとタオル巻いてえぇええ!」
アウリサは平然と湯船を占領しながらつぶやく。
「ナズナちゃんって、綺麗な身体してるよね。脚のラインとか、くびれとか──あ、胸も結構あるじゃない」
「え.....ちょ、ちょと.....なに急に見てんの!?変な分析しないでよー!!」
「だって珍しいんだもん。現代人って服で全部隠すでしょ?王国ではもっと堂々としてたわよ」
「……王国ってどんなとこなの……?」
アウリサとの毎日は、まるで親戚の子供と暮らしているみたいに自然だった。
「ナズナちゃん、王国ではテレビは“魔導映写器”って呼ぶのよ」
「……アウリサー、魔導映写機ばっかり見てないで片づけてー……って、私の隠してたお菓子全部食べてるじゃーん」
それでも、気づけば笑っている時間が多くなっていた。
アウリサは夕飯にもうるさい
ある時、冷蔵庫の在庫をかき集めて、二人は鍋を囲むことにした。
「これが……庶民の鍋……!」
アウリサは白菜をおそるおそる箸で持ち上げ、真剣な顔で観察していた。
「あ、それ白滝。そっちは鶏団子ね。ちゃんと火通ってるから安心して」
「ふふ、ナズナちゃん、なんでも教えてくれるから。好き」
「なんでかな......人にあんまり介入しないタイプなんだけどね」
二人で小皿を取り合ったり、火力の調整で揉めたりしながらも、ふと気づけば笑い声が絶えなかった。
「……これ、あったかくていいね」
「そりゃ鍋だからね」
「違うの!!、心がって意味!!……あー言っちゃったじゃない恥ずかしい」
アウリサは照れくさそうに湯気の中に顔を沈める。
アウリサは夜になると、小さな枕を抱えて「一緒に寝よ?」と尋ねてくる。
「ねぇナズナちゃん。なんかさ、ここにいると、あったかいんだよね。王宮の方が1万倍豪華だけど」
「……質素で悪かったわねー王女様はもう、おねむの時間でしょ?」
ナズナはそっぽを向きながら、隣に布団を一枚敷いた。
騒がしい。とにかくうるさい。でも、
こんな風に誰かと毎日を過ごすことが、少しだけ“家族”ってやつに近い気がしていた。
アウリサは姉なのか妹なのか、それともペットみたいな何かなのか、分類は難しい。
けれどその存在が、自分の生活に溶け込んでいるのは確かだった。
「……ほんと、一人の感じ忘れてきちゃったよ」
そう呟いたナズナの背中に、アウリサの小さな寝息が重なっていた。
そして再び、すれ違い
「だからさっ、勝手に私のズボンをスカートに魔改造しないでって言ってるだろ!」
「だってナズナちゃんの脚、すっごく綺麗なんだもん。見せなきゃ損よ?」
くだらない──でも本人たちには“重大”な、そんな言い合いだった。
ズボンの裾はリボンに変えられ、ポケットは星型の刺繍に置き換えられ、
今日一日着ていた“お気に入りの普段着”は、すっかり魔法少女仕様になっていた。
「おしゃれとかじゃなくて、勝手に変えられるのがイヤなんだってば!」
「でも、似合うから……」
アウリサの声が、少しだけ沈んだ。
「……なんでわからないの。人の服に勝手に魔法かけてくるって、信じてたのが裏切られるみたいでさ……」
ナズナのその一言に、アウリサの表情がピクリと変わった。
「そっか。じゃあ……もう触らない」
短く、冷たく、すねたように呟く。
そのまま、アウリサはナズナに背を向けた。
そして、無言のまま、指先をひと振り。
床にふっと現れた淡い光の円。
ナズナの足元を包むように、魔法陣がそっと広がる。
「ちょ、ちょっと、なに──」
次の瞬間、ナズナの身体が一瞬ふわりと浮かび、眩い光とともに服が変化していく。
ピンクのスカート、フリルのついたブラウス、胸元には小さな魔導宝石。
「は!?うわっ!? な、なにこれ!?また!?!」
ナズナが驚いて声を上げるのも束の間。
アウリサは振り向きもせず、淡々とした足取りでその場を去っていった。
「あっ……ちょ、待って、そういう意味じゃ──!」
言いかけた言葉は届かない。
気まずさと、どうしようもない後悔が、胸にのしかかる。
一人残されたナズナは、変身したまま夜の街を歩いた。
普段なら気にならない視線も、今夜はやけに肌に突き刺さるようだった。
「ああもう……なんでこの格好で外にいるんだ、私……」
ピンクのスカートが風に揺れ、白いリボンが肩口で小さくはためく。
ただのコスプレじゃない。“知らない誰か”になったみたいな気持ち。
(ほんとは──ちょっとだけ嬉しかったんだよ)
誰かに“似合う”って言われること。
朝起こしてくれる人がいて、くだらないことで喧嘩して、でも一緒に笑って……。
それを、アウリサと過ごす中で思い出していた。
たぶん、「家族ってこういうことなのかもしれない。」
ぽつりと独り言をこぼしながら、ナズナは夜の冷たい風の中を歩き続けた。一晩中探してもアウリサは見つからなかった
そして、朝になった。
態勢を立て直すため、一旦帰宅したナズナは、自宅前の階段で、白い小さな影を見つける。
「……遅い。ずっと、待ってたのに」
小さな肩を抱えてうずくまっていたのは、アウリサだった。
白のドレスが朝焼けの光を浴びて、まるで夢から抜け出したお姫様のように淡く輝いていた。
「……なんでそんなとこで……」
ナズナは俯いて、ドアを開ける。
「……ごめんね、言い過ぎたよ。」
「うん......」
アウリサが顔を上げ、涙の跡がキラキラと光を反射した。
その顔が、まるで子どものように無防備で、ナズナの胸にじんと染みた。
「私もごめんね……」
扉が閉まる音とともに、朝の光がそっと部屋の中に差し込む。
まだぎこちなくお互いを深くは知らない、でも確かに、心が重なり始めたふたり。