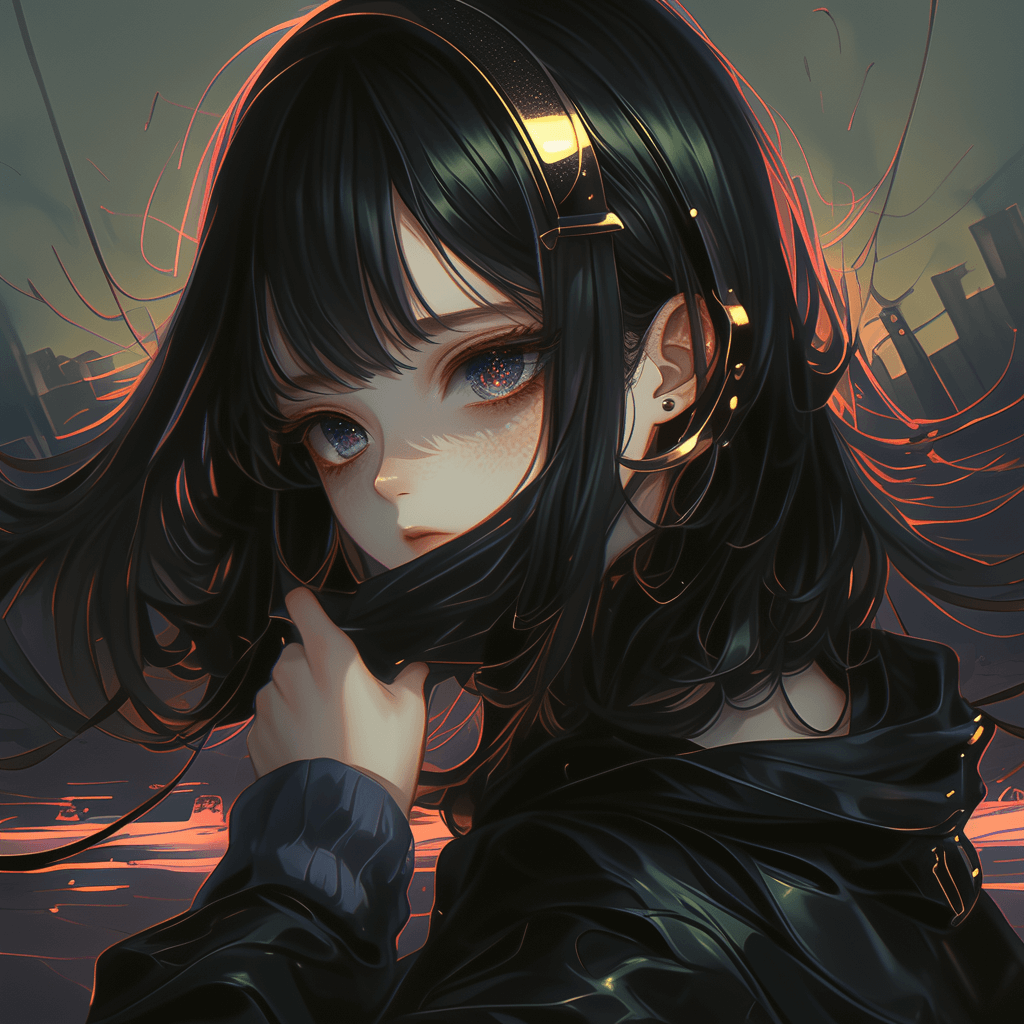
『わたしは、ここで震えてる』──ウズメという名の少女と、静かな光
1. 何も始まらない日々
今日も、空は静かだった。
ウズメは、いつものように学校に着き、教室の端の席にかばんを置いた。廊下の声、教室のざわめき、机にペンを落とす音──全部が遠くに感じる。
「ウズメって、なんか不思議だよね」「よくわかんないけど、ちょっと怖い」
そう言われることにも慣れていた。
返事をする必要も、説明する必要もなかった。だって、自分でもうまく言葉にできない。自分の中で何が起こっているのか。なぜ、誰かが怒鳴りそうになると手のひらが熱くなるのか。なぜ、誰かが泣くと、周囲の空気が震えるのか。
わからない。
ただ、心のどこかで感じる。
──わたしの中に、何かがある。
2. 公園という逃げ場所
授業が終わって、ウズメは家に帰らず、駅前の古い公園に寄った。
ここは、小さいころよく一人で来ていた場所。今でも、ベンチの端に座って、ただ風の音を聞いていると少しだけ楽になる。
遠くの電車の音。町の喧騒、誰にも邪魔されない静かな場所、それはすべてを遠ざけて安心させてくれる。
そうやってぼーっとすると、安心する半面言いようのない不安が胸の奥ですこしずつ痺れのように広がっていく。
3. 家族という圧力
「なんでもっと社交的にできないの?」「他の子はみんなちゃんとしてるのよ」
母の声は優しいけれど強く心に刺さる。
父は無言だった。たまに吐く言葉鉛みたく重かった。
「このままだと、社会で通用しないぞ」
わたしは、社会に認められたいから生きてるんじゃない。
でもそんな言葉、口にしたところで、伝わらないってわかってる。
だから、いつも黙ってる。
けど黙ると、「わかってないって顔ね」とか、「自分の意見もないの?」とか、そんな言葉が追いかけてくる。
逃げられない。
4. 壊れそうな日々の中で
その日、学校で些細なトラブルがあった。
誰かの机が落書きされていて、それをウズメが最初に見つけた。
「え、ウズメじゃないの?」
たった一言。それだけで、空気が変わった。
もちろんやってない。でも否定するだけで、まるで火に油を注ぐように見られる。
静かに立ち去ろうとしたそのとき、誰かの手がウズメの肩に触れた。
「おい、無視すんなよ」
その瞬間、電灯がパチンと消えた。
誰もスイッチには触れていなかった。
「……なんで?」
ざわめきが走る。先生が来て、慌てて場を収めた。
ウズメは、自分の手が震えているのを見ていた。
やっぱり、わたし──普通じゃない。
5. わたしの“ちから”
それが「超能力」と呼ばれるものかどうかなんて、ウズメにはわからない。
でも、怒りや恐怖の波が押し寄せたとき、自分の感情が周囲の空間を歪ませているのを何度も感じた。
小さいころ、雷が鳴った日、家のテレビが爆発的な音で壊れた。公園で絡まれたとき、相手のスマホが発火した。
ずっと偶然だと思ってた。
でも、偶然が何度も起こるわけがない。
「わたし、壊すばっかりだ……」
そう呟いて、またベンチに座る。
「……でも、わたしは、ここにいる」
不安定でも、歪でも、誰にどう思われても。
わたしは──ここで、ちゃんと生きてる。
6. そして、出会い
春の終わりの、少し冷たい夕暮れ。
ウズメがいつもの公園のベンチに座っていると、一人の女性が向こうの道から歩いてきた。
黒い服、ヘッドフォン、金の混じった黒髪──どこか、見たことがあるような雰囲気。
「……この席、いいかな?」
「え、あ……はい」
その人は静かにベンチに座り、何も話さず、しばらく空を見ていた。
ウズメは何か言おうとしたけど、うまく言葉が出てこなかった。
沈黙のまま、数分。
その女性がふと、声を出した。
「ねえ、あなた──何かを持ってるんじゃない?それで困ってたりする?」
「……え?」
「誰にも理解されない力。扱いきれない力。それはちゃんと“ある”って、ホントはあなた自身が知ってるんじゃない?いきなり変な事聞いてごめんね、昔の私に似てたからつい......気にしないで」
ウズメは、驚いて相手を見た。
「わたしは……」
「もし今の私が昔の私に何か言ってあげられるなら、無理に変わらなくていい。自分のままでいい。ただ、その痛みを抱えたまま、少しずつ前に進んでれば、いつかきっと良いことあるよって言ってあげたいかな 」
女性はそう言って、ウズメにいたずらっぽく微笑んだ
「……わたしは.....わたしは....ウズメです」
ウズメの目に、ふわりと涙が浮かぶ。心にある重いモノがポロっと取れたようで自然と涙が出たのだ。
それを見た探偵の様な装いの女性はウズメに、にこっとほほ笑む
女性は立ち上がって、歩き出し、あっさりと去っていった。
7. ナズナの独白
夜、ナズナは端末にメモを残していた。
『今日、公園で一人の少女に会った。名は……ウズメ、だっただろうか。カバンに女の子らしい可愛いマスコットがついていた』
『あの子は、たぶん、まだ自分を知らないし、自分を教えてくれる他人にも出会っていない。でもすごくびっくりした、偶々あんな子に出会うなんて──もしかしたら、一瞬見えたあの力は、あらゆる闇を覆せる程の神々しさがあった。異界の上位存在でも中々いない』(ナズナは生まれつき異次元や霊界などと互換性があり超常的なモノを視認したり、コミュニケーションをとれる能力がある)
『いつか世界を照らす光の手伝いをする、美しく強い存在になれるといいね..........アメノウズメのように。』
ナズナはそっと画面を閉じた。
ウズメ。
この世界に、まだ見ぬ灯が一つ、確かにある。
そしてその少女は、誰よりも傷つき、震えながら、確かに──生きていた。