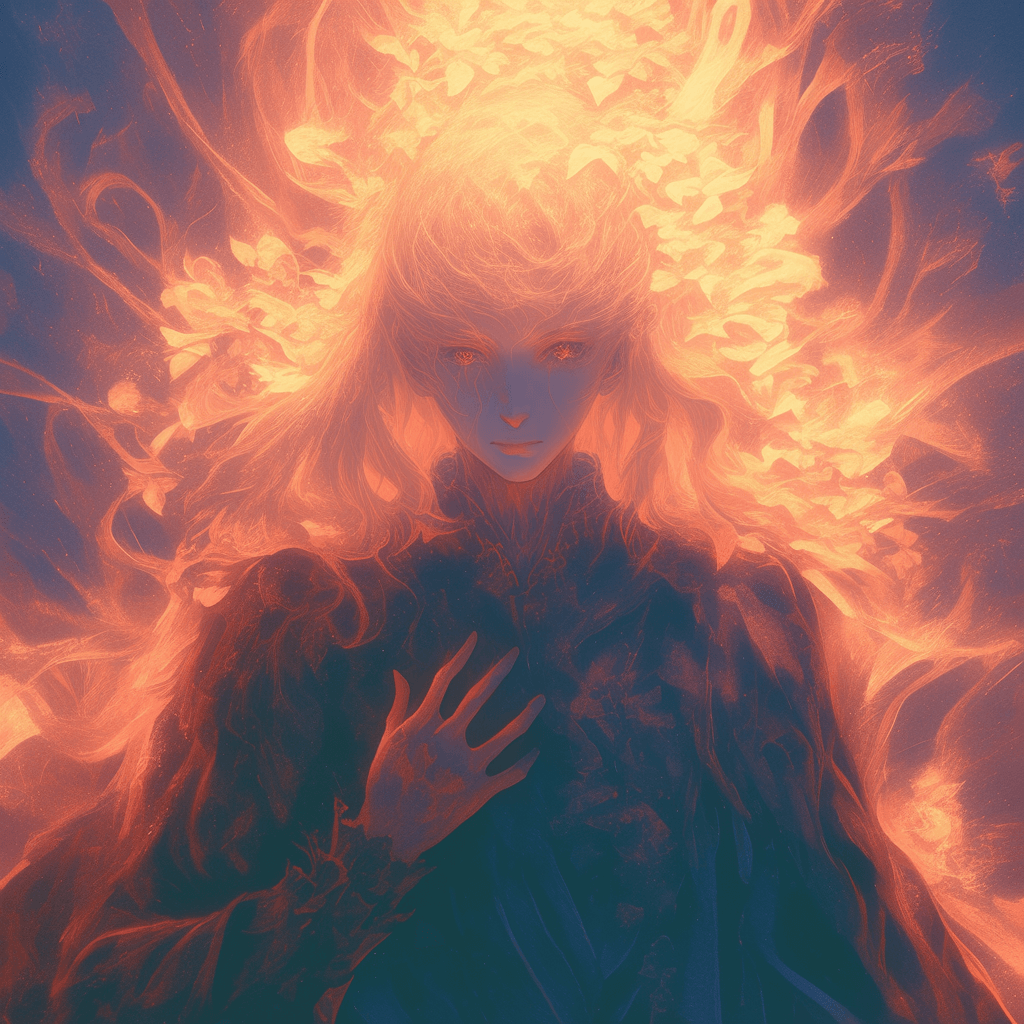
火炎の王 イグニス=レックスの語り
── 我が名は、火炎の王。
この地球とやらに炎を灯したのが我であった。地の底に埋もれていた力を引き上げ、大気に最初の光をもたらしたのだ。
それを“文明の始まり”と呼ぶ者もいよう。
あるいは“災厄の発端”と書き記す者もあろう。
どちらでも構わぬ。
我にとって、それはただの「暇つぶし」の一端に過ぎぬのだからな。
◇
我は何度目かの世界の始まりから在る。
この時の流れも、幾度となく繰り返される“はじまり”と“おわり”のひとつにすぎぬらしい。生まれては滅び、そしてまた芽吹く。
その循環の中で、我は"この5度目の世界の"火の核として、ただそこにいた。
そう──我は、ずっと、この世界の始まりから最前列に座していたのだ。
誰よりも早く“はじまり”に立ち会い、誰よりも遅く“おわり”を見届ける者。
すなわち、“見守る者”としての存在である。
征服しようとも、支配しようとも思わぬ。
力で膝を折らせることなど、我にとっては息を吐くのと同じ──退屈極まりない。
それに、その様な力の使い方をするやつらは嫌いじゃ、薄汚れた心に炎の欠片もない
だが、“燃え上がる者”は違う。
純粋に、己の命を賭して燃える者の心、それを見るのは実に愉快だ。
そう、我が求めるは、
力の行使ではなく、力を超えてなお輝く“意志”そのものよ。
人間の概念はそこまで知らぬが、何かを守る為に燃やす炎は我は美しいと評価はしておる
◇
力について語ろうか。
我が力を、炎と定義する者が多い。
それは正しい。だが不完全だ。
火ではない。
──これは、“神炎”だ。
雷やプラズマ、レーザー光、核融合。
そうした人間どもが定義した火力のすべてを超越している。我も炎に関しては勉強しておる
仮に、核融合とやらは、普段お主らが使う"火"と比べて100000倍の熱さじゃが、我が本気を出せば、それらより遙に爆ぜるはずじゃ。
そうなってしまえば、紅蓮の意志が世界を穿ってしまうがの、そんなことは我は望まん
太陽の核に身を置こうが、
超新星の爆心にあろうが、
我は燃え続ける。
いや、むしろそこは心地よいくらいだ。
この世界に存在する熱源は、すべて我の一部。
あるいは我の残響といってもよい。
我が一振りの咆哮は、地軸を変え、
我が一閃の火炎は、大気の構造を揺らす。
惑星の罪を溶かし
歪んだ思想を焼き祓う
我が焔は、ただ正しき者、弱き者を守り、照らしだす“天の秩序”そのものだ
それが、我。
火炎の王である。
◇
さて、我の悩みについて語ろう。
──退屈だ。
すべてが、退屈なのだ。
力を誇る者は多くいた。
過去、異界の王たち、数多の世界の勇者ども。
だが、すべて“読めてしまう”のだ。
行動、言葉、思想、動機。
──退屈である。
我の前に立つ者がいても、既に結果が見えている。
それが、何より虚しい。
我はずっと、世界がどう変わるかを観察してきた。
いや、もはや観察ですらない。傍観というより、観劇だ。
滅びの劇場、あるいは再生の舞台。
だが、たまに──たまに、例外が現れる。
それが、ナズナである。
◇
ふふ、ナズナ。
お主は面白い。
異界と人界、機械と魔導、記憶と未来。
そのすべての境界を、躊躇いなく歩んでおる。
我と初めて対峙したときの、お主の目──
あれはよいものだった。
恐怖に染まりながらも、思考を止めなかった。
焼かれながらも、推理を進めていた。
まさに、燃え上がる心。
それを見た時、我は思ったのだ。
「これは、しばし見てやろう」とな。
我はお主を少し応援している。
それが面白いからだ。
だからこそ、お主に武具を与えた。
我が“天火の鋒(あまほのほこ)”をな。
奪ったなどとは言わぬ。
授けたのだ。無意識のうちにな。
いずれその槍が、お主の魂と共鳴し、
何かを燃やす時が来よう。
まだまだ、使い方がわかっとらんがな
◇
我が信ずるものは少ない。
だが、信じる者の“炎”はわかる。
──まがったことが、嫌いなのだ。
見栄、嘘、欲、偽善。
そうした“濁った心”には、火が灯らぬ。
燃えぬ火など、我は認めぬ。
だからこそ、ナズナ。
お主には燃え続けて欲しい。
心の焔を絶やさずに、
清く、まっすぐに、我をも凌駕する炎を灯してみせよ。
──それが見られるなら、
この退屈な世界にも、価値があるというものだ。
◇
いずれ再び会おうぞ。
いにしえの娘よ。
その時は、火炎の王としてではなく、
一人の観客として、お主の舞いを見ることにしよう。
……楽しみにしておるぞ。
ふふ……フハハハハッ!